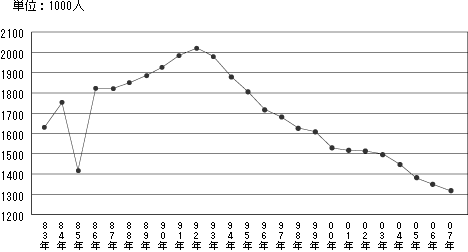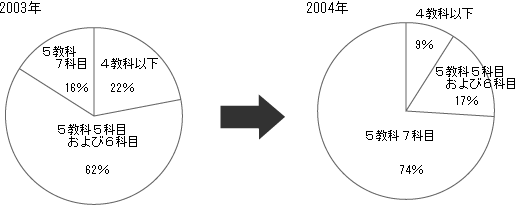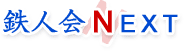
| ■ 難関大への受験(44) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -英作文に強くなる2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前回に引き続き、英作文対策を考えたいと思います。英語の記述式試験では、英作文を出題するところが多くあります。過去問の解説には、いくつかの例が挙げられていますが、覚えている何千語の英単語や英熟語とうまく結びつけることが、第一のコツです。
例として、2004年度富山医科薬科大学前期の英作文(大問Ⅰ~Ⅴのうちの5番目;入試時間90分)です。 Ⅴ 次の下線部の文章を英語に訳しなさい。 七十年以上も生きていたから、いろんなことがあったに決まっているが、ことさらに失敗と思い込んだ記憶がない。根が気楽なたちだから、昔のことを気にしないということもあるが、それよりは何かの目標を設定してそれを達成する生き方が性に合わなかっただけのことかもしれない。(森毅) 「気にしない」、「気楽なたち」、「性に合わなかった」など、日本語独特の言い回しの処理に工夫がいります。 1) 前半: 1.「根は」は、もともと(originally)や、生まれつき(naturally, by nature)と当てはめられそうです。 2.気楽なたち(性分) → 楽天的な性格(optimistic)あるいは楽天家である(be optimist)ということで、いままで習った英単語で処理できそうです。 3.「気にしない」は、mind, worry about, care ,not consider ―――― as bothering などが考えられます。 4.「こともあるが、それよりは~のこと」は、比較を表しています。 理由の「一部は、だけど大部分は」として、partly, however, mainlyや、rather than(これだと、日本語と順番が入れ替わりますが)が使用できます。また、下線部は「記憶がない」ことの理由を説明する文章なので、becauseを添えます。 5.[~だから、~しない]には、頻出のso ~thatが使えます。 前半のまとめとして、 根が気楽なたちだから、昔のことを気にしないということもあるが、は、 Partly because I am originally so optimist that I never mind the past things, 2) 後半: 1.「目標を設定する」→「目標を決める、目標を定める」などと、解釈できそうです。 2.「生き方」に「何かの目標を設定してそれを達成する」という、長い修飾がついています。関係代名詞をもちいて、the life way in which~ とできそうです。修飾部は、I decide some aim(goal, objective) and make it come true などとできます。 3.「性に合わない」というのは、「適合しない、不適当である、好きでない」と解釈でき,Iam not fitted for doing, Icannot adapt to, Ido not like to, などとかけます。 従って、後半の文章、それよりは何かの目標を設定してそれを達成する生き方が性に合わなかっただけのことかもしれない。は以下のように書けます。 however, mostly because I am fitted for the life was in which I decide some aim and make it come true. 英作文では、答えは十人十色で、たくさんあります。赤本などの過去問の解説では、多少違った表現を使用することがありますが、自分の応用しやすいものから真似するといいです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(43) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -英作文に強くなる1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今回は、英作文対策を考えたいと思います。英語の記述式試験では、英作文を出題するところが多くあります。ちょっとしたコツがわかっているのといないのとでは、スラスラ書けるか全く書けないかの、大きな違いになると思います。
例えば、次の文章を英訳する場合を考えます(2002年自治医科大学の英語の入試問題中の英文(?~?の内の?)の一部です。 冒頭文の、医学分野は人間の生活を高める大きな可能性を秘めている。を訳します。 第一文:医学はmedicineであり、医学のという形容詞は、medicalです。この単語は、大学受験志願者には必須のものの一つでしょう。医学分野(medical field)を主語とした骨格を考えて、作文できます。 次に、「人間の生活を高める」ですが、いくつかの表現が考えられます。いかに、既知の語句と結びつけるかが作文のコツです。まず、日本語の他の言い方を考えると、 1;人間の生活の質を高める、2;人間の生活のレベルを上げる、3;人間の生活を発展させる、などがあります。 まず、1について、人間の生活の質「quality of human life」をどうするかと考えると、直接「高める」という他動詞の単語(promote, enhance, improve, raise)などから当てることが考えられます。Enhance(発展させる)、promote(促進させる)、improve(改善する)、raise(増加させる、上昇させる)ことから考えると、improveやenhanceの目的語にすれば、英文がつくれそうです。あるいは、「より高い質の人間の生活」を「導く」、「生じさせる」としても、英文らしくなりそうです。lead to a higher quality of human life, give rise to a higher quality of human life などが書けます。 2について、動詞として、レベルを上げる(level up)を当てれば、level human life up が考えられます。 3について、発展させるとして、enhance, developなどの必須単語を思い出し、それらを他動詞として使用します。 更に、「大きな可能性を秘めている」ですが、まず「可能性」を絞ります。大学受験必須単語として、possibility、probability、capability、likelihoodが思い出されます。他に、「潜在性、潜在能力」として、potentiality(potential)があります。「大きな可能性がある」と考えれば、There is a great possibility(potentiality)that ----あるいは、have a great possibility(potentiality) to ---、と書けるでしょう。 以上、解答としては次の文が挙げられます。 1: Medical field has a great possibility to improve quality of human life. 2: There is a great possibility that medical field levels quality of human life up. ちなみに出題文は、The field of medicine has great potential to enhance human life.となっていました。語彙力と連想力をあげることで英作文が随分楽になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(42) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -自然科学分野の英語を覚えよう 単語6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英語の入試問題では、自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあるということで、特集を組んでいます。自然科学分野に限らず、英語読解でとても役に立つ表現を集めました。
1) 生物学 その2 facility: 施設、接備、能力 いろんな英文によく出てくる単語です。facilitate(動詞;促進する、亢進する)とfacilitation(名詞; 促進、亢進)と併せて覚えるといいと思います。accelerate(動詞;加速する)やacceleration(加速、促進)と類義語といえます。 feasibility: 可能性 類義語として、possibility(実行可能なこと), probability(見込み), capability(能力のあること), likelihood(期待できること、見込みのあること)があります。形容詞は、feasible(実行できる)です。 kernel: 核、仁、粒(grainの意味)、種、穀粒、動詞;仁を生ずる これらの生物学的な意味から、中心部、心髄、眼目(gist)の意味もあります。 invertebrate: 無脊椎動物 ←→ vertebrate(脊椎動物) vertebra(脊椎)から来ています。類義語として、spine(背骨、脊椎)や、spinal cord(脊髄)があります。 larva: 幼虫、幼生 ←→ imago(成体、成虫) latency: 潜伏期、潜在性 覚えておくと、英文を読むとき役立つことが多いです。他に、隠れていること、見えないもの、といった意味があります。latent(形容詞;隠れている、潜伏性の、休眠の)も合わせて覚えたいです。 lateral: 側部の、傍系の 横の、外側の意味から来ています。lateral branch(側枝), lateral root(側根)、lateral bud(側芽)などとして使用します。化学用語としては、lateral chain(側鎖)があります。上述のlatentとよく似た綴りなので、要注意です。 lineage: 血統、系統、一族、親族 line(直線)が接頭にあるので、意味がとりやすいと思います。Linage(一直線、行数)とも同語にも扱われます。形容詞は、Lineal(直系の、正統の)で、linear(直線の)に通じます。 maternal: 母系の ←→ paternal(父系の) mama,papaと通じる単語です。 migration: 遊走(卵子など)、渡り(鳥類)、回遊(魚類)、渡り鳥、移動動物 migrate(動詞;移動する、移民する)の名詞形の意味の一つです。英文では、移動、移民の意味でもよく見られますが、移動することからこちらの用語もあります。immigration( 入国、入国管理、移民、移住)と併せて覚えると、覚えやすいです。 mold: カビ、糸状菌 moldにはいろんな意味があります。1つめは、かたち、鋳型、かたどる、2つめは、地面、腐植土、浄土、表土の意味です。そして、生物のカビもよく見られます。 mollusc (mollusk):軟体動物。Molluscaで軟体動物門 primate: 霊長類(Primatesで霊長目) 他に、大主教、大司教、首長、指導者の意味があります(prime(第一の)に通じます)。やはり、動物で最も高等動物なという意味が込められているのでしょう。 segment: 分節、体節、セグメント 切片、区分、部分の意味から、他分野の用語ともなっています。例えば、線分、扇形(数学用語)、音あるいは分節(音楽用語)などがあります。section(部分、区分、節、地区、欄、分隊、切片)の類義語です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(41) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -自然科学分野の英語を覚えよう 単語編5- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英語の入試問題では、自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあるということで、特集を組んでいます。自然科学分野に限らず、英語読解でとても役に立つ表現を集めました。難しい単語もあると思いますが、興味のあるものから眺めてみてください。
1) 化学分野 affinity: 親和性、親和力 この名詞の他の意味として、親近感、共感、魅力、類似性(生物学の用語)があります。 alignment: 整列、整列化 動詞のalign(aline)の派生語です。Line(線)の語句が入っているので、整列する、一直線に並べるという意味は、想像しやすいですね。~と緊密に協力する、提携するという場合には、align against(with)~となります。 anabolism: 同化、同化作用 ←→ catabolism(異化、異化作用) anabolic(形容詞;同化の、同化作用の)が派生語であります。Metabolism(代謝)、metabolic(代謝の)と関連して覚えるといいと思います。 bond: 結合、価標、 名詞として、帯、縄目、束縛、契約、保証金や、動詞として、束縛する、接着する、結合するの意味があります。接着剤の「ボンド」もこの語句からついたのでしょう(英語の発音では、バンドなので、音楽関係のほうのことばにもなりますが。) combustion: 燃焼、(有機体の)酸化 burn(燃える)に通じる単語です。Combust(動詞;燃料を燃やす、燃料を消費する)、combustible(燃えやすい)などの派生語があります。 conjugation: 抱合、共役、結合、配合、接合(生物の) この語には、英文法の「活用」の意味があります。動詞conjugateは、1)文法を活用させる、2)化合物を共役させる、3)結合させる、の意味があります。 また、数学理学でも使用され、conjugated point(共役点) conjugated diameter(共役直径)conjugated angle(共役角)などの用語にみられます。生化学では、conjugated protein(複合タンパク質)がよくみられますし、生物学のconjugant(接合個体)の用語もあります。conjugal(形容詞;婚姻上の、夫婦の)も関連用語です。 degeneracy: 縮合 degenerate(動詞;、縮合する、変性する、退化する(生物学)、堕落する)の派生語です。 excresion: 排泄、排出 Ex(外へ)の接頭語がついているのでわかりやすいです。excrete(動詞;排泄する、排出する)Excrement(排泄物、排出物、糞便), excretory(排出の、排出器官 excretory organsと同じ意味の名詞として)などが派生語としてあります。英作文では、dropping(糞)やwater(尿)として書くほうが書きやすいでしょう。類義語として、同じcresionがついている、secresion(分泌)、secrete(分泌する)をセットで覚えてしまうといいと思います。 lavage: 洗浄 lave(動詞;洗う、浸す、水浴する)から来ている単語で、lavatory(手洗い所)に通じます。 Lavation(洗浄、洗浄水)とwashingが類義語としてあります。 Penetration: 浸透、透過、浸透力 他に、貫通、透視力、洞察力などの意味があります。動詞のpenetrate(浸透する、通す、貫通する、染みこむ、印象付ける)もよく使用されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(40) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -自然科学分野の英語を覚えよう 単語編4- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英語の入試問題では、自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあるということ
で、特集を組んでいます。今回は、物理分野です。なにか、普段の英文とはかけ離れた単
語になりそうですが、さにあらず。語彙力をつけるのにとても役立ちます。
1) 物理学: adhesion: adhere (接着するという動詞)からの派生語で、接着、物理的癒着を意味します。adherence(接着性、精神的癒着)との区別に注意します。 abrasion: 摩擦 abrade(動詞:すり減らす、すりむく、神経をすり減らす)の派生語です。 charge: 充電、電荷 動詞では、充電する以外に、負担させる、請求する、委託する、突撃する、などの意味があり、名詞としては、代価、料金、責任、委託、突撃などの意味があります。熟語としては、in charge of(に委託されている、に預けられている、の担当の)、take charge(責任を引き受ける)、make a charge against(~を非難する)などがあります。 反義語は次のとおりです。 discharge: 放電、放出 動詞では、放電する以外に、降ろす、吐き出す、放出する、排出する(排泄する、eject)、果たす、履行するなどの意味があり、名詞としては、放免、解除、履行、荷揚げ、発射、医学用語の排出物、分泌物、うみ、やに、鼻汁があります。 compression: 圧縮、加圧、 compress(動詞:圧縮する、加圧する、要約する)の派生語です。Press(圧力)があるので、判りやすいです。医学で、圧迫、圧迫症の意味です。 conduction: 伝導、誘導 conductance: コンダクタンス(抵抗の逆数)、伝導力 conductivity: 導電率、伝導性conduct(動詞:振舞う、導く、作曲する。名詞の意味では、行為、経営、管理、指揮、 )の派生語です。他に、conductive(形容詞;伝導の)、conductor(導体、導線、伝導体、案内者、指揮者、車掌、管理者(manager))などがあります。 critical: 臨界の 批判的な(形容詞)の意味でまず覚えることが多いのですが、他に危機の、きわどい、重大なという意味があるので、そこから上述の用語になります。critic(名詞で、批評家、鑑定家、批判者、形容詞で批判的な)、criticality(臨界、危機的状態)、criticize(動詞;批評する)、critique(名詞; 批評法)、criticism(評論、批判主義)などの派生語もあります。 Interference: 干渉 Interfere(動詞:inをよく伴い邪魔する、妨害する、withをよく伴い衝突する、抵触する、勝手にいじる)の派生語です。生化学のインターフェロン(interferon;ウイルス抑制因子 に通じます。 Elasticity: 弾力性、弾性 名詞として、他に融通性、伸縮性、明朗さ、順応性などがあり、Elastic(形容詞;弾性のある、伸縮自在の、屈託のない)、elasticize(動詞;に弾性を持たせる、伸縮性を持たせる)などが派生語です。 reflection: 反射。反射作用、反射光、反射熱、反射音、影、映像、反転、屈折部 reflectance: 反射率 他に、名詞には、黙想、熟考などの意味があり、随筆などの文章でしばしば見られます。派生語には、Reflect(動詞;反射する、反映する、熟考する、非難する(on をつけて、blame onと同じ)、reflex(形容詞;反射した、反射作用の、反射的な、反射型の、反省する、名詞;反射運動、神経などの反射作用(生理学)、考え方、像、写し)などがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(39) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -自然科学分野の英語を覚えよう 単語編2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英語の入試問題では、自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあるということで、特集を組んでいます。専門分野だけでなく、どんな英文を読むときでも、とてもいいヒントになります。今回は、生物学について、いくつかの単語をあげていきます。
1) 生物学 acclimation: 順化、順応。 climate(気候)が入っている単語です。acclimateあるいはacclimatizeが、生物(ヒト)を新環境に慣らす、順応させるという意味があるので、その用語として使用します。acclimatizationも同じ意味です。 alga: 藻類、藻類の 生物の種類をさす単語は、生物学に限らず一般の文章でも出てくることがあるので、機会があればできるだけ覚えておくと便利です。 Amphibian: 両生類、両生類の Containment: 封じ込め Contain(含むという動詞)の派生語で、containmentは包含、牽制の意味もありますが、理科でも閉じ込めることや生物学的な封じ込め(地理的隔離など)も意味します。Container容器、コンテナも頻出の派生語です。 development: 発生、発達 develop(発生する、発達するという動詞)とともに、英文で非常によく使用されています。生物学的意味でも使用します。形容詞のdevelopmental(発生上の)も覚えたいです。 deviation:偏向 逸脱、偏りの意味から、生物進化上の偏向の意味もあります。deviate(動詞:脱する、名詞:変質者、偏差値)の派生語も要注意です。 differentiation: 分化 difference(違い),different(違いのある)でおなじみの単語の派生語です。細胞や組織に違いが生まれることなので、やはりここから用語ができています。 division: 分裂 devide(分けるという動詞)の名詞の「分けること」の意味があるものの、生物学の文章では 細胞分裂の意味で使用します。Fissionも同様の意味です。 dominance: 優位(動物個体間の)、優性(遺伝学)、優占度(生態学) dominate(動詞の支配する、優位に占める)の派生語として、支配や優越(ascendancy)の意味がありますが、生物学的にも重要な用語になります。dominant(形容詞:支配した)は、優性の、優占したという意味になります。 envelope : 外被、包膜 envelopeは、封筒、包むことの意味から、生物学の構造や、数学の包絡線の意味まであります。envelopは動詞で、包む、覆うの意味です。 fetus: 胎児、胎仔 Fungus(複数Fungi): 菌類、真菌、カビ、キノコ、筋腫 覚えておくと、英文を読むときにとても便利です。 Heredity: 遺伝、遺伝形質 世襲、伝統という意味もありますが、生物学的にも使用します。Hereditary(形容詞)は、世襲制の、代々のという意味と、生物上の遺伝性のという意味があります。 Hibernation: 冬眠 Hibernal(形容詞:冬の、寒冷の)や、hibernate(動詞:冬眠する、引きこもる)の派生語としてあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(38) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -自然科学分野の英語を覚えよう 単語編1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英語の入試問題では、自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあるということで、特集を組んでいます。最近は、英語と合わせた小論文や総合問題での出題が目立ちます。ここでは、自然科学向きの語句を整理してみます。
まずは、分野別の専門用語にはいるけれど、英語全般でよく使用される単語集です。かなりの単語を知っているひとでも、結構穴になりそうな単語が沢山あります。まずは、数学分野です。 1) 数学分野: addition: 加算、足し算 add(加えるという動詞)の派生語で、加えることを意味していて、in addition to(~に加えて)という熟語でよく知られています。数学的に、足し算(加算)に訳するほうがいい場合もあるので、文脈で判断します。 arc:弧、アーク。 弓形、弧状に動く、の意味もあります。Arch(アーチ)と arcade(アーケード)は、同じ派生を持ちますが、意味の違いに注意します。 convergence: 収束、収斂。 converge(一点に集まる、収束する、収斂するという動詞)の派生語で、収束を意味します。convergency(収束性)や、convergent(収束のという形容詞)という派生語があります。 digit:桁 指(finger)、足指(toe)指針(index)という意味もあります。 dimension: 次元 3次元空間(three dimensional space)などのように、数学だけでなく一般の文章でも使用されます。 expansion: 展開、展開式 Expand(展開するという動詞)の派生語で、英語の文章でしばしば見かけます。数?から習う、展開式の英訳です。 fraction: 分数、有理数、端数 通常は、破片として習いますが、同じ破片でも、分離した一片は分数となります。また、細分するという動詞も同じで、化学や生物では、画分、蒸留の留分となり、さらに分割の意味もあります。Fracture(割れ目、破面、医学の骨折)にも通じる単語です。 Function: 関数 機能、作用、職務、行事、儀式という名詞や、機能する、作用するという動詞としても頻繁に使用している単語です。 index: 指数 索引、目録、指針、目盛りなどの意味もありますが、数学用語としても使われます。 integral: 積分の、整数の Integrate (統一する、総和するという動詞)の派生語として、integral(絶対必要な、完全なという形容詞)がありますが、数学的用語としての意味もあります。その他の派生語は、integration(積分法、統一、完成、調整)や、integrant(構成要素の、絶対必須の)などがあります。 mean: 平均の、平均値の 意味する、意味でもよく使用される単語ですが、averageの同義語として覚えている必要があります。 multiplication:掛け算 加減乗除の英語表現は、覚えておくと英文を読む時とても助かります。動詞のmultiplyとともに覚えておきたいです。5に3を掛けるは、multiply 5 by 3となります。 population: 集団 人口の意味でもしばしば使用されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(37) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2次試験プラス私大受験直前準備 英語編その2 リスニング編--自然科学分野の英語を覚えよう その1- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国公立2次試験や私立大学の英語の入試問題では、随筆や会話文、小説のほかに自然科学分野の文章を出題するところがしばしばあります。特に、後期日程の問題では、英語と合わせた小論文や総合問題で、専門分野の論文の一部が出題されることも多いです。ここでは、自然科学向きの文と語句を整理してみます。まずは、ちょっとした気分転換のつもりで、読みにくい箇所があっても、あまり気にせずに気楽に見てください。
自然科学分野の英語の特徴は、キーワードとなる専門用語の繰り返しが多いことです。 例えば、次の文章を見てください。2000年度 自治医科大学 英語問題 ?(?~?の冒頭部です。 A few years ago, organ transplantation was legalized in Japan. However, the debate still goes on whether brain death in truly human death. The following is the opposing argument to legally recognizing brain death as human death. First of all, brain death is totally different from the traditionally-accepted (concept) of death in Japan, which regards heart stoppage as human death. 和訳:2,3年前、臓器移植が日本で法律的に正答となった。しかし、いまだに脳死が本当のヒトの死であるかどうかは議論されている。次に示すのは、脳死をヒトの死として法律的に是認することに対する反対理由である。第一に、脳死は、日本で伝統的に受け入れられてきた死の概念、すなわち心臓停止をヒトの死とみなすことと全く異なっている。 上述の太字の単語は、医療分野の専門用語となっています。しかし、基礎的な単語の組み合わせなので、結構読みやすいです。例えば、organ transplantationは、organ(器官、機関、オルガン)とtransplantation(移植)からなる熟語なので、「臓器移植」と推定できます。そのうち、transplantationは、すぐに意味がわからなくても、trans(移動)と plantation(植え付けること、農園、プランテーション、人工林、建設)の組み合わせからと、文章全般の意味から「移植」がふさわしいと推定できます。特に、新聞やニュースで社会的な出来事を見聞きしていれば、これが最近の臓器移植や脳死の問題の英語版と想像ができます。これらの単語は、もっと医学的な用語、例えば、cortex(皮質)やfocus(病巣)などよりはずっと把握しやすいし、それなりの英語力があれば把握できるものです。 一方、下線部は、英語全般を使用する時に重要な単語で、高校課程から大学受験に掛けて、重要単語として習うものです。とても専門的な単語であれば、注釈がつくと思いますが、英語全般から見て重要な単語だと、故意に注釈を載せない場合もあるので、受験に必要な単語をしっかり覚えることが大事です。 まずは、高校から大学受験で習う必須単語を広げる意識を持ちたいです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(36) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2次試験プラス私大受験直前準備 英語編その2 リスニング編--入試直前準備 見直し項目 理科編- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入試前になると、実践的な過去問を解いて仕上げに入ります。今まで充分勉強してきた人は、かなりの高得点がマークできるかもしれませんが、入試1セットの問題中で、誤答は1つはあるものです(満点はとりにくい)。度忘れや単純ミスで誤答することも多いです。
入試直前には、完全に覚えたつもりでも、必ず覚えていなければならない用語や内容を一通り見直しすることをお勧めします。しばらく勉強していないと勘が失われて、細かい用語や、不意打ちの問いに答えられにくくなります。過去問を解く合間に、使い慣れた用語集や参考書をみれば、ほっとするという安心効果もあります。 理科の各科目で特に強化する見直し点は、次のようになります。 化学: 記述式では、化学?・?Bに加えて化学?が範囲に入るため、有機化学などの細かい知識が問われやすくなります。最重要の基礎的知識に加えて、詳細も少しずつ確認していきたいです。 例えば、生ゴム、弾性ゴム、エボナイトの違いを説明するとき、加硫という、生ゴムに硫黄を加える操作によって、架橋結合をつくり弾性ゴムが生成し、架橋結合が多いとエボナイトになるということになりますが、専門用語を多く使用して詳細を説明することになります。 難関入試の大半は頻出タイプの問題の集合ですが、解答量が膨大で時間が足りないくらいのセットもあります。時間内に解答できるように、過去問のセットを何回か解答して時間配分を研究していきます。 物理: 頻出問題でよく使用する計算や考え方を確認し確実にします(おそらく充分練習してきたと思いますが)。さらに志望大学の問題傾向をよく研究して、必要なレベル以上の問題に取り組みます(応用問題、発展問題)。暗記する項目は特に多くないと言われていますが、問題によっては、重要な用語や公式を小問で書かせることがありますから、できるだけ漏らさず得点できるようにチェックします。例えば、(粒子性と波動性、E=hν、定常波、コンプトン効果など)。 生物: 生物では、記憶する用語や内容が非常に膨大で、しばらく勉強していないと、とても勘が失われやすい科目といえます。また、医歯薬学部では、生物学の細かい知識、例えば人体の臓器構造の細かい部位や生物の特徴など、ほとんど教科書では扱われない内容が問われることがあります。今まで使用してきた参考書などで、詳細を確認します(重箱の角を突付くくらい)。 特に、記述式では、生物?の範囲が多く出題されます。例えば、遺伝子の転写と翻訳、分類や進化などが狙われます。進化の年表や代表的な動物と植物を直前まで丹念に見直しをしたいです。 地学: 惑星の軌道などの計算問題の取り組みは物理と共通するものがあり、土壌成分は化学と共通するものがあります。 直前期に家庭教師と授業をする時には、不意打ちの問いにも動じないように、家庭教師と一緒に能率よく確認したいです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(35) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2次試験プラス私大受験直前準備 英語編その2 リスニング編- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入試直前期の対策を考えています。前回の英語長文に続き、今回は、リスニング対策を行います。
現在の大学受験英語はリーディングが中心で、リスニングを取り入れている大学・学部は一部です。小学校から高校までのリスニング授業が学校によってまちまちなことや、音声設備の手間の問題があるからでしょう。もしリスニングが入試問題に含まれている場合、その他の試験準備と違ってとても厄介です。 第一に、赤本などの過去問にリスニングの文章が書いてあっても、一人では練習できません。試してみると判ります! 例えば、2004年度のリスニング問題が書いてあったので、さあ、解いてみようとします。ところが、その文章を読む誰かがいないことに気がつきます。「聞き取り」の練習なので、誰かが話している英語を聞いて、問いに答えないと意味がないのです。入試のリーディング(読み)やスピーキング(過去問の文章を一人で音読しているといったほうがいいかもしれませんが)の練習は独自にできるのに、残念です。そのような問題の対策として、市販されている英検や英会話のリスニング用問題集には、CDがついているものがあり、英語を母国語とする人の会話が録音された問いを聞いて練習するようになっています(それなりに高価になります。一冊2000円ぐらい。)。でも、大学受験の過去問にはついてないですね。 このような入試用のリスニングにこそ、英語の家庭教師はぴったりだと思います。家庭教師が過去問を読み、それを聞き取れば練習できることになります。たとえスピードや発音で、アメリカ人やイギリス人と多少異なることがあっても、ある程度の雰囲気は掴めるでしょう。多くの入試問題のリスニングは、ゆっくりとしたスピードで読まれ、しかも1回きりではなく、2回繰り返し読まれることがあります。従って、かなりの英語力がある人は、リスニングテストでも実力にあった得点がそれなりに期待できます。しかし、いくら英語力があっても、練習がゼロか一度でも行ったことがあったかどうかでは、実際の試験に向かう時の状態が大変違います。精神的にも随分リラックスできます。 どうか、家庭教師におまかせください!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(34) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2次試験プラス私大受験 直前準備 英語編その1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今回は、国公立大学2次試験と私大入試に向けて、直前に効果的な勉強方法を考えていきます。特に、英語は大部分の入試の受験科目になっており、しかも配点が大きいことが多いので、直前までしっかり準備したいですね。
まずは、毎日のように英語に触れることをお勧めします。少なくとも長文を一問(大問1問など、一つの文章になっているもの)を少しずつ読む習慣を持っていれば、長文を読み込む勘やスピードが衰えることはないでしょう。他教科の準備もあって英語から遠ざかることがあれば、以外と勘が失われやすいのです。 読む長文としては、受験する大学の過去問、おさらいしたい問題集の長文問題などが中心になるでしょう。今の時期の勉強法で、特に大事なのは次の方法です。 1) 試験時間を考えて、一問にかかる時間を計算し、時間内に解くことを計算します。 例えば、試験時間が60分で、大問(第1問、第2問など)が全部で3つあれば、20分弱の17、8分ぐらいが1問にかける時間の目安となります。60分の3分の1の20分より2、3分少なめなのは、見直しの時間を考えています。難問を解く場合、時間が足りないくらいになることもありますが、他の大問で調整するように練習するしかないでしょう。常に時計と見比べて解答する習慣を持つことは、とても大事です。本番の試験であわてずにすみます。 2) 文章中に知らない単語が出てきても、そこで留まらないで全文章を通して読みます。 受験生のみなさんは、おそらく今まで数ヶ月以上かけて準備をしてきたはずで、理想的には長文を読むテクニックがほぼ完成している時期です。また、単語や熟語も多々覚えているはずです。しかし、それでも難しい文章では、意味がわからない単語が1つ2つ出てくるときがあります。不明な単語はとても気になるものですが、辞書にたよらない習慣を仕上げなければなりません。文章からできるだけ単語の意味を推定して、他のわかる単語で読解します。また、単語の接頭語(pre(前)、sub(副)、ex(外)など)や接尾語(able(可能))や意味のある節(tension(張)、motive(動)など)である程度意味が推定できます。例えば、interrelationが出てきた場合、長い単語なので慌てると、何だ?ということになりますが、よく見れば、inter(内)とrelation(関係)の足し算されたもので、「相互関係」という意味になります。 それから、生活を朝方にして体調を整えることを忘れないでください。どうしても準備不足を感じても徹夜勉強を続けて生活を乱すよりは、勉強時間を制限して集中的にするほうが結果的にリラックスできます。 最後まであきらめずに限りある時間を合格のために有効に使用したいですね。何か不安があるときには、どうか家庭教師に尋ねてみてください。直前のまとめに集中的にお手伝いできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(33) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -直前対策 数学その2 類似問題を解く- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大学入試センターの出題は、毎年よく似た問題が出題されています。直前期には、その決まった型の問題を集中して解答することが、一番の対策となります。
数学の場合、数学?・Aと数学?・Bに分かれており、その内容は、次の通りです。 数学?・A 第1問(必修):二次関数と個数の処理 第2問(必修):数と式と三角比 第3問(選択):数列 第4問(選択):平面幾何 第5問(選択):コンピュータ 数学?・B 第1問(必修):三角関数と指数関数・対数関数 第2問(必修):微積分と図形と式 第3問(選択):ベクトル 第4問(選択):複素平面 第5問(選択):確率分布 第6問(選択):コンピュータ これらの設問を踏まえて、直前期には次のチェックが大事になってきます。 1)時間配分の確認: センター試験は、試験時間が短いのが特徴です。特に、数学は1997年の新課程以降の問題で、時間の割には数多くの問題が出題されるようになってきました。試験時間60分を守って、1年分を通して解くだけでなく、各問題に掛ける時間のペースを大体掴んでいることが要求されています。 例えば、各問題に掛ける時間の目安は次のようになるでしょう。 数学?・A 第1問:22分(二次関数で約12分、個数の処理で約10分) 第2問:22分(数と式で約12分、三角比で約10分) 第3問:12分 第4問:12分 第5問:12分(第3問から第5問までを1問選択) 数学?・B 第1問:15分 第2問:15分(第1問と第2問合わせて30分前後) 第3問:12分 第4問:12分 第5問:12分 第6問:12分(第3問から第6問までの2問で24分ぐらい) 数学?・Aと数学?・B各60分の中に、見直す時間5分程度を見込んでおくと、少し余裕ができます。また、折角解けていても、途中で計算間違いをしていたり、マーク位置がずれていたりすることは、毎回のようにあることです。このようなケアレスミス防止のためにも、ざっと見直す癖をつけているといいと思います。 2) 公式、定理の確認: 使い慣れた参考書や問題集には、必ず重要な公式や定理がまとめて書かれています。例えば、表紙や裏表紙の見開き(左右で2ページ)に、それらが一覧で列挙されている本が結構あり、直前期にはとても便利です。それらを使って、よく使用される式をさっと見直しておくだけで、随分リラックスできます。解の公式や数列の式など、複雑で細かい式の符号や指数を確認するだけで、試験時間中の数秒が節約できるかもしれないのです。確かに難問ほど数分は解法を考える時間が必要になりますが、必須事項を迷っている時間はほとんどありません。 3)誤答しやすい設問に絞ってまとめの演習: 1年分を通して解くこと以外に、各設問の時間配分に従って、苦手な単元を解いていくことは、時間がないときに有効です。旺文社の速講 数学?・A(あるいは数学?・B)センター試験予想問題集など、センター試験と類似した問題を集めた受験本は役立ちます。10日間完成などコンパクトなタイプのものもお勧めです。 4)選択問題を決めておいて、時間を節約する: 数学?・Aと数学?・Bの後半は選択問題で、どれを選択するかが大きく影響します。試験前に決めておくほうがやりやすいことは多いです。ただし、例えばベクトルと複素平面は似ていることもあり、両方ができる人にとっては、その場でどちらが易しい問題が出題されたか即断するほうが、メリットがある場合もあります。また、自分が得点しやすい問題から解いていくのも一手です(例えば確率分布など。同時にマークの位置に注意)。 5)各設問の後半に時間がかかりそうだったら、前半だけ解いてしまう方法もあることを思い出す 6)自分にとって難しい問題は、他の受験生にも難しい。 直前期には、なにかと不安になりがちですが、受験を経験した家庭教師に相談する機会が一度でもあれば、自分の抱える困難は他の人にも同じなことがわかります。また、最後のまとめも他の視点からできるのでなにかと役立つことがあります。どうか、最後の1秒まで有効に準備してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(32) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -マークシート英語編- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大学入試センター試験直前期には、集中的にマークシート対策を考えていきます。今回は、英語です。
センター試験の英語は、2次試験の記述式の英語に比べると、比較的易しい文章が出題されます。ですから、記述式から離れてリラックスしてできる場合もあります。しかし、試験時間が60分と短く、その間に確実に処理していかなければならないので、油断大敵です。 センター試験は、毎年同じ傾向の問題が出題されているので、それらを集中的に演習すると効果的です。各問題は次の内容で、毎年よく似た問題が出題されています。 第1問: アクセント、発音、文の強勢問題 第2問:文法、語法、語彙問題、会話問題、語順整序問題、 第3問:接続詞、前置詞・副詞句の空欄補充問題、短文整序問題、 第4問:図表付き説明文の読解問題、 第5問:会話長文問題、 第6問:長文読解問題、 確かに、英語は膨大な語句や表現を的確に覚えて使用しないといけないので、時間がかかります。しかし、あきらめは禁物です。いままでの勉強や出来が充分でなかったとしても、試験直前に最も必要なことは、最後の1秒までできるだけ準備をすることです。試験数日前になっても何十時間以上の時間はあるわけで、できることは沢山あります。 1) 誤答しやすい問題に絞って演習する: 予備校や出版社のセンター模擬試験は、上述の形式に沿って作成されています。更に、センターの過去問を解いてみたことがあれば、自分で間違いやすい設問がどれか把握しているはずです。直前期には、その苦手な設問に絞って数回は演習すること、知識を補足し慣らしておくことが必要です。赤本や、各予備校の過去問集、センター試験対策と書かれた問題集をもう一度復習しておくことをお勧めします。また、家庭教師に1,2回相談してもらうだけでも、客観的に見つめ直してコツがつかめることがしばしばあります。 2) 発音、単語、文法の要点をおさらいする: 各受験生は、単語集や文法の本を使って一通り覚えてきたはずです。それら使い慣れた受験本をさっと見直し、あるいは要点集にしぼってもう一度確認しておくだけで、随分リラックスできます。 発音の種類についての出題は、平成14年以降からなくなっているものの、よく問われる発音については、しっかり押さえておく必要があります。 3)時間配分を確認しておく: センター試験は、各正答に対して紛らわしい解答候補が1つは混ぜてあり、最新の注意を払わないとできないように工夫されています(簡単には得点させてくれない!)。時間内に正確にマークするためには、解答の時間配分を充分に練習しておくことが大事です。試験時間通りに解いて自分のペースを確認します。 このように、直前期に粘り強くまとめを行えば、私大や2次試験の準備がとても行いやすくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(31) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -マークシート対策 生物編2 実験考察問題- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生物のマークシート対策として、次の3つが柱になることを前回提示しました。
1) 問題中の語句や文章を正確に読解して、それに沿った解答をする 2) 実験の考察問題を意識して演習する 3) 忘れている用語、曖昧な内容がないかときどきチェックする 1) については、前回で、具体例とその対応を述べました。今回は2)についてじっくり見ていきます。 生物は暗記だと言う人がいますが、とんでもない!確かに、暗記する用語や内容が非常に多いのは事実です。植物や動物(人体を含む)の種名から部位の名前に始まり、その機構(遺伝、循環系、排出系、生態系)などなど盛りだくさんです。しかし、センター試験の生物を見ればわかるように、年々実験からの考察問題が増えています。例えば、20001年度以降の生物?Bのセンター試験(本試験)では、大問6問のうち、実験や図表からの考察問題は、次のようになっています。 2001年度: 第1問 細胞分裂: 実験からの考察が中心と基礎用語 第2問 窒素代謝: 教科書の知識を問うのが中心 第3問 発生: 教科書の知識を問うのが中心 第4問 遺伝: 表と設問から考察する 第5問 動物の行動: 複数の図表を組み合わせた実験考察問題 第6問 土壌生物のはたらき: グラフの解読 2002年度: 第1問 植物の極性: 実験1と実験2で考察問題 第2問 酵素: 教科書の基礎を問う問題と、グラフの解読 第3問 脊椎動物の発生: 教科書の知識を問う問題と、 実験考察問題(図表の組み合わせ) 第4問 遺伝: 表を解読して計算 第5問 本能行動: 複数の図表を組み合わせた実験考察問題 第6問 海洋の生態系: グラフの解読 2003年度: 第1問 細胞分裂: 実験からの考察が中心 第2問 代謝(呼吸): 実験考察問題と教科書の知識を問う 第3問 両生類の受精と発生: 実験考察問題(実験1と実験2) 第4問 遺伝: 表と実験から花色の遺伝について計算し考察する 第5問 動物における体内環境の恒常性: 図からホルモンについて考察する問題と、教科書の知識を問う問題 第6問 動物個体群の構造: 図と説明文から実験結果を考察する問題と、教科書の七期を問う問題 2004年度: 第1問 動物の分裂と増殖: グラフからの読解、教科書の用語を問う問題と、実験考察問題 第2問 糖の代謝: 教科書の知識を問うのが中心 第3問 ウニの発生:教科書の知識を問う問題と、実験1と実験2から考察する問題 第4問 遺伝: 伴性遺伝についての知識と遺伝計算 第5問 動物の行動:ミツバチの8の字ダンスについての考察と、ゴキブリの触覚について実験1と実験2から考察する問題 第6問 生態系における植物の窒素利用: 教科書の知識を問う問題と、表の数値からの考察問題 以上のように、第1問:細胞分裂や細胞構造について、第2問:呼吸や光合成について、第3問:発生など、第4問:遺伝、第5問:生物の行動、第6問:生態系と、ほぼ定番の内容が定位置にあり、しかも、大半が実験考察問題を含んでいます。実験考察問題は、未知の実験の過程と結果を問われたり、教科書や参考書に載っている内容を踏まえつつ、より複雑な機構を考察させるのが特徴です。 その対策としては、日頃から論理的推察力を訓練しなければなりません。教科書や参考書の内容を覚えるだけではとても足りず、また質の異なる訓練でもあります。内容と用語の整理に加えて、図表や実験を提示した演習問題を数多く解答して、原因から結果を導く訓練をする必要が大いにあります。家庭教師は、論理的にどこまで考察しているか、文章や解答選択で詳細にチェックしていますので、どうかじっくりと尋ねてみてください。 次回は、センター試験の問題を使って、実際に考察していきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(30) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -マークシート対策 生物編- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
センター試験が近づいてくると、マークシートに対応した勉強を多くすることになります。1997年度以降新課程に対応してセンター試験の内容はより難しくなり、着実な学力をつけていないと、高得点はとても望めなくなりました。どの科目でも、考察力、速読、読解力、計算力をふくんだ高度な総合力を要求しています。そこで、各科目毎に、最も効果的な対策をたてていきたいと思います。今回は、理科の生物対策を考えます。
理科では、化学と物理を2科目として選択する受験生が多いのですが、生物を選択する受験生も増加しています。生命科学に関連した医歯薬農学部等の受験では、入学前から生物を必須科目に指定したり、入学後の履修に備えて受験に望ましい科目として考えられる場合があります。また、文科系受験者は、物理より計算が少ない生物のほうが選択しやすいかもしれません。 生物のマークシート対策として、主に次の3つが柱となります。 1) 問題中の語句や文章を正確に読解して、それに沿った解答をする 2) 実験の考察問題を意識して演習する 3) 忘れかけていたり曖昧な内容がないかときどきチェックする 1) の、「問題中の句や文章を正確に読解すること」は、国語をはじめとする他教科と密接に関連する重要なことです。設問に沿った解答をすることは最も大事なことですが、慌てて単純な勘違いをして惜しい誤答をしがちです。例えば、正答を知っていても、「最も適したものを選びなさい」と「間違った内容の番号を選びなさい」では、全く異なった解答となります。 例として、センター試験2001年度 追試験 第1問 の問2を見てみましょう。 第1問 細胞に関する次の文章(A?B)を読み、下の問いに答えよ。 細胞に関する研究の進歩は、顕微鏡技術の発達と密接な関係があった。17世紀に、フックは手製の顕微鏡でコルクの切片を観察し、 ア コルクの内部がたくさんの部屋に仕切られていることを見つけ、その部屋を“細胞”と名付けた。 以下省略 問2 下線部アでフックが“細胞”と呼んだ構造は、実際にはどのようなものであったか。下線部アの部屋とその仕切りに関する記述として、最も適切なものはどれか。次の?から?のうちから1つ選べ。 ? 部屋は中空で、その仕切りは、小さな細胞がたくさん集まったものでできている。 ? 部屋に透明な細胞質がつまった、大きな1個の細胞でできている。 ? 細胞壁が厚く、液胞の発達した1個の細胞で、部屋の部分は液胞である。 ? 1個の死んだ細胞でできており、原形質が失われているため、部屋は中空である。 まず、下線部アで「たくさんの部屋」、「その部屋について」といっているので、「その部屋」は一個の細胞(a cell) 、「たくさんの部屋」はその部屋の複数( cells)で, 組織(system)の一部を指していると解釈されます。 コルクは植物の死細胞の集まりなので、生細胞の記述は該当しないことになります。 ? では、小さな細胞がたくさん集まったもの( cells)とあるので、該当しないとわかります。 ? では、部屋に透明な細胞質がつまった(生細胞)とあるので、該当しないとわかります。 ? では、液胞の発達した1個の細胞(老化した植物の生細胞の特徴)とあるので、該当しないとわかります。 ? 1個の死んだ細胞、原形質が失われ、部屋は中空と3つの記述がコルクの1細胞に最適とわかります。 このように、設問の一語一句を的確に読解する訓練に、家庭教師はじっくりとアドバイスしています。どうか尋ねてみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(29) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -小論文編2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以前の回で、少しだけ小論文対策について書きました。今回は、更にヒントになることを、引き続きお伝えしようと思います。それは、論文の構成についてです。必ず小論文を書くときの参考になります。
皆さんが大学に入学した後は、必ず論文を書くことになります。卒業論文や、授業の単位のために書くレポートなどです。そして、論文作成には、必ず参考にして重要な語句を引用する本や雑誌が必要です。それらは、「参考文献」あるいは「引用文献」と呼ばれ、必ず本の後ろのページに一覧が出ています。大学での参考文献や引用文献は、主に専門分野の学術雑誌に掲載された論文です。論文は小論文(800字から1000字程度)に比べて、通常字数あるいはページ数は多くなりますが、その骨格となる構成は同じです。専門分野のどんなにエライ権威者学者も、そのルールに従って書いています。 小論文や作文では、よく「起承転結」と言われます。文章の構成は、「起」で問題提起をし、「承」でその問題を受けて詳細を述べ、「転」でその問題とは少し異なった内容を述べ、最後に「結」で結論を述べてまとめる、ということです。そして、この手法は、専門分野の論文、学術論文にも生かされており、英文にも和文(日本語の文章)や他言語の論文にも共通しています。 例えば、自然科学部分野の論文では、題目(タイトル;Title)、著者名と著者の所属先(Authors)、要約(摘要,;AbstractあるいはSummery)、緒言(イントロ;Introduction)、材料および方法(Materials and Methods)、結果(Results)、考察やまとめ(Discussion, Conclusion)で構成されます。題目は、本文の内容を的確に要約した最小単位で、キーワードが必ず含まれます。緒言では、その研究分野の背景、研究調査を行う必要性について述べます。材料および方法では、その実験調査に使用した材料や器具(たとえば、化学薬品の硫酸や実験器具のビーカーなどもれなく記述します)、方法(化学、数式や方程式(どの数式に従って計算したか)、概念や理論などを整理して書きます。結果は、材料および方法を実行した結果について簡潔に表示します。図表(グラフや絵も)や写真でわかり易くまとめられています。考察とまとめは、その結果から考えられること、意義を述べます。仮説と同じであったかどうか、今後どうすべきか、などを述べます。緒言が「起」であり、承が「材料および方法」であり、「転」が結果、「結」が考察とまとめに該当します。自然科学論文ではかなり物質的な感じがしますが、小論文や作文を構成する要素が、より具体的で物質的になっているようなものです。小論文は、なにを構成要素にしていくかを整理して構造を決めることで、出来の良し悪しが大きく左右されますから、この学術論文はとても参考になるはずです。 英語長文の自然科学分野の出題も、これに従った構成で書かれています。随筆ではやや砕けた体制になっている場合もありますが、それでも近い構成には必ずなっているはずです。英語の時にもどうか参考にしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(28) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -小論文編1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小論文は、他科目に比べて、得点を明確に予想しにくいところがあります。その割には意外と配点が高く、例えば、国立大後期試験が論文と面接だけの学部学科も多いので、侮れない科目でもあります。
小論文の要素は、国語の中の現代文にもあります。東大の前期試験では、数百字程度で作文をさせる問いがあります。理系受験では、国語を受ける必要がない人もいるでしょう。しかし、大学に入学したら、レポートや卒業論文、学術論文は必ず書く必要があるわけで、小論文のポイントはなんらかの参考になるはずです。 確かに、稀に作文の才能に恵まれている人はいて、将来小説や評論で生計を立て、名だたる作家になることもあるでしょう。一流の作家ほど、独特な語句、文章の展開、着眼点が精妙であり、流れのある印象深い作風をもっています。まあ、そこまではいかないまでも、できるだけ読みやすい説得力のある文章を書ける訓練をしておくと、必ず役立ちます。履歴書や就職について書く重要な書類にしても、誰かにお願いしているわけですから、文章力が主な能力とも見られるわけです。 筆者の例でいうと、国語は好きで、作文もそれなりに得意なほうでしたが、模擬試験で作文を添削してもらうと、期待した得点がもらえない場合が時々ありました。そこで、ある程度練習すれば、得点の上がり下がりが少なくなって安定しましたが、内心は、なにか手馴れていない、光る言葉のない自分の文章を不満足に思っていました。大学の学部生以後、文章を書く機会が増え、どんどん書いて、書き直して、そして他人に読んでもらうことを繰り返すうちに、随分書くことに慣れてきたと思います。長い時間をかけて練習して、多少なりとも文章の流れを掴んだようです。思うに、10代から数えれば何年もかけて、個人的にいろんな経験をし、もともと好きだった読むこと(新聞、雑誌、などなど)を繰り返したことが、ものを書くための訓練になったと思います。 やはり、小論文対策は、できるだけ多く文を書くこと、できるだけ他人に読んでもらうこと、できれば添削してもらうことだと思います。これは、国語対策、特に現代文に通じることです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(27) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -国語(現代文編)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国語は、現代文、古文、漢文で構成されています。古文や漢文では独特の単語や表現を丹念に勉強していなければ解答できないのに比較して、現代文は私達が日頃使用している言葉で構成されているので、慣れているとたかをくくってしまいがちです。それで、勉強しないでぶっつけ本番で試験を受けている人も多いようです。しかし、これでは、得点の上がり下がりが大きくなってしまいます。受験の合格は、常に安定した点数を獲得する訓練をしないと困難なのことですので、国語でギャンブルをすることになりかねません。
特に、センター試験の国語?と国語?では、200点満点のうち、現代文100点(評論50点と小説50点)、古文50点、漢文50点となっており、現代文が半分を占めています。 つまり、現代文は思っているより比重が大きいのです。以外と、得点差をつくり出しているといえます。侮らずにじっくり対策を考える必要があります。今回は、見逃されがちな現代文の得点アップに効果的な方法を考えます。 現代文の問題は、1)重要な漢字熟語や文法、慣用表現に対する設問、2)段落や接続など文章構成に対する設問、3)文章全体の要点を問われる設問、4)文章中のある文の意味を問われる設問、5)キーワードに関する質問、などがあります。 1) や2)では、主なものは中学校までで学習しているので、誤答をしないで確実に得点することが大事です。忘れがちな語句は、大学受験用の参考書や本などで手早く確認しておくといいと思います。 評論は、現代文とはいえ、各文が長く複雑なので、3)、4)、5)で解答が難解な場合があります。そこが、得意不得意の差が出やすいところといえるでしょう。まずは、文章全体を読みこなす対策を考える必要があります。日頃からの読書量や演習量が読むスピード、理解度に強く影響を与えるでしょう。評論対策のために新聞(特に社説)を読むことは、国語でよくいわれることです。マークシートで選択する解答文は、かなり長く複雑なものや類似した文も多いので選択に苦労します。重要なのは、設問の一語一句が指す内容を正確に読み取り、本文と合致するかどうかを掴む練習を積むことです。 小説の場合でも、読書量や演習量をふやし、正確に語句や内容を掴む練習をするのが一番です。評論に比べると、心情表現の解読が要求されるので、日頃から感情を言葉で表現することを意識しているといいと思います。 家庭教師とは、言葉一つ一つの意味を話しあうことで、文章の理解力がついていきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(26) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -常に高得点を維持して合格するための秘策- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
難関大学に合格するには、総合点で高得点が必要となります。苦手科目で点数が伸びないと、得意科目では絶対満点を取りたい!と意気込みたくなります。私は、以前「先生、僕は数学が苦手なので、生物でいつも満点を採らないといけないんです。なんとかしてください!」と高3生に言われたことがありました。気持ちはわかるのですが、難易度が高いテストで常に満点を採るのは大変困難だと思います。
基礎的なテストやセンター試験に代表されるマークシート形式の試験では、満点が要求されることがありますし、実力が培われていれば満点がとれる場合もあります。しかし、どんなに満点が取れそうでも、体調や問題との相性で、1,2問を間違えてしまうことはよくあることです。満点を過剰に期待すると、数点分間違えただけでとても気落ちしてしまいますから、精神衛生上からみても、あまりいい目標とはいえません。 一番大事なのは、常に高得点(7割や8割の得点率)を維持することです。これ以外に、合格への確実な道はありません。例えば、各大学の合格圏といわれる得点率が発表されています。東大受験では、センター試験で約87%の得点率が必要であるとか、偏差値75以上が必要であるなどと提示されます。東大の2次試験(前期)の合格ライン得点率は、総合点(440点満点で、センター試験は110点分に凝縮する)の6割以上、理科?類で7割以上と通常いわれています(各年度で多少変動します)。他の大学や学部でも、難関受験の合格ラインは7,8割であることが多いのです。つまり、満点でなくても、7,8割を確保する実力をつけておけば、十分合格できるのです。しかも、合格者の最低点であっても、合格になります。一番で合格する必要は特にないのです。 合格のためには、基礎問題と標準問題はほぼ完璧におさえておき、常に正答する必要があります。スポーツや芸術では、すでに身につけた技術をいかに発揮できるかで、ほぼ成功が決まります。全く未知のことが要求されるのは比較的少ないものです。入試でも同じで、勉強した基礎問題や標準問題をしっかり解答することです。これらの問題で正答できないのは、度忘れや読み間違い、書き間違いなど、ケアレスミスが以外と多いものです。そのようなケアレスミスをなくすだけで、数点から数十点違います。 実力を正確に発揮すれば、どんな模試でも得点率が安定してきます。得点率や合格ラインに変動があるのは、実力が完全に身についていない証拠です。運良く得意な問題が出題されれば得点が上がり、苦手な問題だったら解答できないから点数が下がります。そのような未完成な部分は、自分で気がつかなくても、他人(特に家庭教師)にはよく判ります。実力完成のためにも、家庭教師によく相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(25) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -解説理解と自力解答のちがい- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お元気ですか?
今回は、自力で入試問題を解答することは、解答の解説を授業や本で理解することと、相当な隔たりがあるのだということを、あえて強調してみたいと思います。 予備校や高校の授業で、演習問題の解説を聴きます。講師や教師によって流暢に解説されるので、問題をスラスラ解答している感覚になります。授業前に予習して思いつかなかった解法も、瞬時に話されてすっきりした気分になります。また、新しい着眼点に出会って目からうろこが落ちる思いになることもあります。 しかし、ここで、思い出してください。これは他人が書いたり語ったりしたことを理解した状態であって、自分で解答できたわけではないということです。例えていえば、バーチャル・リアリティであり、進行が定まっているテレビ番組を受動的に受けているのと似ています。つまり、類似問題が出題されても、なにも見ないで自分ひとりで解答できるとは限らないわけです。確かに、完成度が高い人は、すぐに見聞きした手法を取り入れて次に使うことができる場合もあります。しかし、それはごく少ないことです。通常は、解けなかった問題や類似問題を、後で何回か解いてみて徐々に覚えて確認していくもので、当然時間がかかります。 家庭教師の授業が集団授業と違うところは、集団授業では生徒がほとんど受動的に解説を受け取って、個人の予習や復習を期待しているのに対し、家庭教師は生徒が解説を受動的に理解しているだけなのか、本当に自力で思いついて解答をすすめているのか、見極めながら授業をすすめられるということです。家庭教師も、必要な時には連続的に解説することがあります。しかし、それに加えて、家庭教師はあえて生徒に着眼点を質問したり、数式をたててもらって、自力で理解し解答できないところを自覚してもらうことがあります。家庭教師のヒントなしで解答できないということは、自力ではまだまだ解答できないということをあからさまにします。 どうか知己(己を知る)ということばを心に刻んで受験に向かって努力して欲しいと思います。そして、集団授業では経験できない、家庭教師の指摘を糧にしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(24) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -応用力をつける方法2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前回、入試問題には、1)基礎的で必ず得点源にしなければならない設問、2)基本問題に比べてやや複雑になっているものの、標準レベルで解答できる設問、3)高度な思考力を必要とするので時間がかかる設問、の3種類があると説明しました。通常は、1)と2)が70%あるいは80%を占めているので、ここで確実に得点していくことが、合格を手にする鍵となります。実はこれらは、突出した才能はあまり必要がないのです。基本事項や頻出問題をコツコツと積み重ねて勉強していくことで、かなりの得点が確保できます。大半の受験はこれが最大の戦略です。そのリズムをつかめない時に、家庭教師や予備校に相談して、受験まで準備をしていくことになります。
しかしながら、大学の学部や学科によっては、問題の一部に極めて特異な出題をすることがあるのは事実です。私大を中心に、教科書からぎりぎりはずれないような詳細を問う出題も見られます。予備校や塾などでは、模試や問題集で、難関大学向けに難問奇問を出してくるので、なおさら気になってしまいます。難関大学志望者は、基礎と標準を固めながら、上級レベルの問題集を解いていくのが一番だと思います。赤本もそうですが、大手予備校では難関大学向けの受験問題集を出版しています。例えば、駿台文庫の駿台受験シリーズでは、レベル別(入門レベル、基礎レベル、中級レベル、上級レベルなど)の表示があります。また、河合出版では、難易度が高いものとして、2005入試攻略問題集(各教科)(各分野)、こだわって!国公立二次分野別問題集がありますし、代ゼミライブラリーでは、大学別プレ問題集があります。また、数学や物理では、「大学への数学」の難問(Cレベル)や大学教養レベル問題集(解析学や幾何学)に挑戦することで、腕試しできるかもしれません。 これらの上級レベルの問題集は2次の記述試験向けですので、100%自力で解答できないことが時としてあります。2次試験では、配点の60%から70%の得点ができれば合格ということが多く(医学部では80%以上もありますが)、常に100%の得点は望まれてはいないものです。その場合、難問や時間がかかる問題は後回しにして全く解答しないこともあります。しかし、練習では時間のかかる難問も含めて検討していくことで、思考力が鍛えられます。解説をよく読んで、新しい発見が生まれることもあります。また、志望大学や志望分野専攻の家庭教師に尋ねることで、上級レベルの思考がとても鍛えられるでしょう。そのような家庭教師は、試験の状況をよく判っているだけでなく、大学でより専門的な内容を学んでいるため、詳細な解答や解説ができることが多いのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(23) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -応用力をつける方法- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験シーズンが近づいてくると、ますます模試や入試問題の出来不出来が気になります。基本問題ができても、そのような応用問題や難問は苦手にしている人が多いようです。
基本問題は、素直な問題がほとんどです。要点を見て重要事項をそのまま記入したり、1つの公式に当てはめると解ける問題がほとんどです。それはそれで最初の段階で大切なことですが、そこから如何にして応用していくかが、思考の見せ所といえます。 各教科の入試問題や模試は、次の3種類に分けられます。 1) 基礎的で必ず得点しなければならない設問: 最重要な用語や公式、単元の項目になっている語句を1つずつ書かせるもの。上述の基本問題に該当します。 例えば、 化学:電気分解、同位体、重要な物質の分子式を書かせる、 生物:細胞内の呼吸の場はどこか? 答え:ミトコンドリア、 社会:メルカトル図法、バビロン捕囚、性善説などの用語を書かせる 数学、物理:最初の小問(1)で、x=1などとして簡単な計算をさせる、次の問題のヒントになる、などどあります。 2) 基本問題に比べてやや複雑になっているものの、標準レベルで解答できる設問:問題集や入試過去問題で演習を繰り返しておけば、大抵は得点が見込めるもの。 各教科の問題集では、標準レベルやB(A基本、B標準、C発展、応用、難問*)と書かれていたり、赤本の解説では標準レベルの問題、などど評価があります。 その教科でも、問題文がある程度長文になっていて、考察して解答するように工夫されています。 3) 高度な思考力を必要とするので時間がかかる設問:常に得点は難しく、うまくひらめくことができれば、部分的にでも得点できるかもしれない問題。その教科によほど精通していないと難しい。 数学や物理では、最難問の問題、大学教養レベルの問題を正答する訓練が必要となります。大学への数学の難問(Cレベル)などにじっくり挑戦していくべきでしょう。 また、国語や英語では、難しい単語や表現が多い長文に慣れることが必要となり、 社会や理科(生物、化学)では、設問に長文を読んでそこから複雑に考察し、細かい計算をしていくことになります。 通常は、1)と2)が70%あるいは80%を占めているので、ここで確実に得点していくことが、合格を手にする鍵となります。そのために一番必要なことは、日常の勉強を積み重ねて、安定した実力を備えていくことです。自分ひとりでは、着実に1)と2)を吸収していく手ごたえがないときには、どうか家庭教師に相談してください。家庭教師と一緒なら、3)に捕らわれて、1)と2)を疎かにすることがないようにメニューを組むことができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(22) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -科目相関の意外な利用- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験生の皆さんは、受験科目が多いので苦労することが多いと思います。英語、数学、国語に加え、理科と社会で選択科目を受験しなければなりません。1科目だけでも理解し覚える内容が多いので大変です。
よく言われるのは、内容的に関係のある科目を選択して勉強することです。例えば、数学と物理は三角関数の頻繁な使用など関係が深いため、理系受験者は、必修の数学に加えて物理を選択します。数学と物理では、方程式を導いて解答するセンスにも、共通点があります。また理科内や社会内では、単元が重複しているものもあります。例えば、化学と物理(気体の状態方程式や運動など)、化学と生物(高分子化合物、分子式、浸透性など)、世界史と日本史(日本と海外の関係)、世界史と倫理(思想史、宗教史など)があります。これらは、科目同士が分野的に近い間柄なので、内容や要求されるセンスが同様なのは当然といえば当然ですね。 しかし、科目間の深い関係は、これだけに留まりません。例えば、設問を一字一句正確に把握する能力は、国語の読解力と非常に関係があります。記述式での文章作成能力も同様です。国語とは割りと縁遠いような数学でも、読み方一つで全く異なった条件を設定しなければなりません。 例題を挙げると、 問題:定数pに対して、3次式方程式x3-3x2-p=0の実数解の中で最大のものと最小のものとの積をf(p)とする。ただし、実数解がただ一つのときには、その2乗をf(p)とする。pがすべての実数を動くとき、f(p)の最小値を求めよ。(東大) 与式「x3-3x2-p=0の実数解」とあるので、この方程式を微分して図式することを思いつきます。g(x)=x3-3x2とy=pの共有点を考えるパターンが多いでしょう。そして、実数解で最大と最小とあるので、最大(x=M)と最小(x=m)とすれば、M×m=f(p)としていることがわかります。「ただし」以下は、M=mのときもM×m=f(p)とすることを意味しています。「pがすべての実数解を動く」とあるので、y=pをx軸に平行に動かして考えます。(答えは、M>0、m<0として考え、M×mの絶対値が最大の時を考えると、f(p)の最小値は-3となります) このように、一字一句を読解して数式化する必要があります。 結局、ある一つの科目を得意にすることは、他の科目を得意にすることでもあります。事実、上位レベルの学力の人は、どの科目も得意な場合が多いのです。難関大学の各受験科目では、まんべんなく高得点率が出されて(要求されて)います。 私は、家庭教師としてある科目を担当した場合、科目の相関を強く意識してアドバイスしています。まずは、その科目の問題や内容を丁寧に解説しますが、生徒が吸収できそうなときには、他の科目と重複するような内容を一緒に説明しています。そのほうが、総合的な思考力を養い、複数の科目を得意にできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(21) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -マークシート形式と記述式対策- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
みなさん、お元気ですか。受験は体力勝負なので、体調管理は常に心掛けてくださいね。
さて、大学受験の場合、センター試験に代表されるマークシート(選択肢)形式と記述式の2つのタイプがあります。国公立大受験では、通常センター試験と大学独自の2次試験が課せられています。私大受験では、受験者数が多いことに対応して選択肢式が多いものの、記述式も見られます。選択肢しか出題しない大学のみを受けるつもりの人は、記述式を特に意識して勉強する必要はないのかもしれませんが、大半の人はマークシート形式と記述式の双方に対する勉強をする必要があります。 マークシート形式の場合、複数の候補から正答を選ぶことになります。解答候補の語句や文章は、重要な用語や表現がちりばめられています。思い出すのが苦手な語句や内容の時には大助かりです。つまり、解答候補自体がとてもいいヒントになっています。一方、記述式の場合は、多くは頭の中で完全に暗記し整理された内容を元に解答しなければならないことが大半です。従って、記述式対策では、生半可な暗記や理解では太刀打ちできません。本を読んで暗記が不十分なら、覚えるべき語句を何回も書いたりまとめたりして完全に覚える必要があります。それは、特に、英語や社会、理科で必要になるでしょう。一語句を書かせる場合のみならず、10字程度から300字程度の文章を書く場合にも、素早く確実に思い出してまとめないと、とても時間内で解答できないことが多いのです。 しかしながら、マークシート形式でも難しい点があります。選択肢をえらぶ場合、解答候補がとても類似していることが多く、選択する時に表現の違いを注意深く見極めて選択する必要があります。また、マークシートの塗りつぶしや選択した記号を書く場合、解答前後が似ているので解答欄が間違いやすいということがあります。更に、数学や理科の計算問題では、計算した数値を塗りつぶしたり選択したりするので、結局記述とかわらず重要公式を思い出して自力で計算をする必要があります。 結局、記述式とマークシート形式の双方で受験を予定している場合は、第一に記述式を意識して勉強を進め、時々マークシート独自の模試や練習問題で演習して慣れていく必要があります。それは、できるだけ早い時期から進める必要があるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(20) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -暗記科目が得意な人へ もう1ランクアップするために2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理数系は苦手だけど語学や暗記が強いタイプの人に向けて、得意科目でもう1ランク実力を上げる工夫について、以前お話しました。今回は、同じタイプの人が、理数系科目の実力アップをするときのヒントになるお話をしたいと思います。
誰でも得意不得意があるものです。全受験科目が同じように得意という人はわずかです。苦手意識から自分を卑下する必要はないですし、言い訳をして無意味に敬遠するだけでは問題克服にならないと思います。なぜ不得意なのかが自覚できれば、それに向けて対策をたてて時間をかけて努力していくしかありません。すぐに結果がでなくても、全部が理解できなくても、少しでも上達すれば自信がつきます。長い人生のなかで、今後あらゆる困難があった時に問題解決するいいヒントになると思います。 第一に数式を使うことや計算が苦手で嫌いになってしまうことが多いようです。なぜ重要な公式や定理ができたのか、その重要性はなにかについては、教科書や授業の中で必ず説明され証明を習います。実は、これが一番難しく根本的で最重要なことなので、理解するのはとても大変です。まずは、そこから苦手意識を持ってしまうことがあると思います。数学や物理など理数系分野を専攻していく人はその深い理解を要求されますが、そうでない分野へすすむ人は必ずしも必要ではないことを思いだしてください。まずは一番基本的で最低限必要な勉強からすすめるのがいいと思います。 例えば、大半の入試問題は、適切な公式を暗記してその数式に値を代入することで解答できます。頻出問題は、使用する数式や解法を暗記して何度も挑戦していけば解けるようになるはずです。類似問題を数問解いていけば、結構覚えていけると思います。一番簡単で暗記しやすい基本問題から、計算を練習していけばいいわけです。文科系での受験であれば、発展問題や応用問題まで出題しない場合もあるでしょう。欲張らず少しずつで十分だと思います。 それでも、理数系科目になかなか取り組みにくい場合には、家庭教師と一緒にすすめれば慣れやすいと思います。家庭教師は、適切な練習問題を選択して、解答しやすい流れをつくってあげられます。一人で苦しいことでも、二人で取り組んで適切なアドバイスを受けることで随分楽になるはずです。どうかお任せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(19) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -暗記科目が得意な人へ もう1ランクアップするために- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)理数系が強いタイプの人と、2)理数系は苦手だけど語学や暗記が強いタイプの人に向けて、もう1ランク実力を上げるアドバイスしています。今回は、暗記科目が得意だけど理数系科目は苦手という人向けに、ヒントになるようなお話をしたいと思います。
暗記科目といわれる科目は、社会(世界史、日本史、地理、現代社会、倫理、政治経済)、英語、生物などがあります。これらは、暗記する用語や事項が他科目と比べて多いのでそう呼ばれるようですが、「丸暗記科目」と思われているのはちょっと残念です。丸暗記である程度簡単な問題演習がこなせても、応用問題、難解な入試問題は丸暗記だけでは到底こなせないはずだからです。 暗記することはある程度必要ですし、能力の一つです。しかし、暗記だけでは人真似に終わってしまう、自分自身の独自の思考や表現をしていないということで、低い評価になってしまいます。例えば、私達が日頃使っている日本語にしても、幼児期から、一語一語を真似て何回も練習してこなした結果として、難解な文章や細かい表現をこなしています。 その時、記憶された語句が適切に絶妙に使用されてこそ生きてきます。なにげない日頃の会話にしても、簡単なことばを上手にタイミングよく使うと話がはずんで心の交流ができるものです。 暗記が得意な人は、記憶した用語や内容を整理してできるだけ理由立て理論立てて覚えることで、より実力がアップすると思います。 例えば、世界史や日本史にしても、ある歴史的事件が起こるのには理由があったわけで、その関係国や人物、事件の結果などの状況を整理していくと一括した内容として覚えられます。1274年と1281年の文永の役と弘安の役の背景として、元とフビライ体制、日本の鎌倉幕府と日本の情勢と、それぞれ原因と結果があったわけで、それらの関連事項を整理していくとより判りやすいと思います。 また、理科の生物や化学でも、ある現象を暗記するだけではなくて秩序正しく整理していくととても勉強になります。生物でいえば、神経伝達をめぐる神経細胞などの部位(樹状突起、軸索、神経末端など)をただ暗記するだけでなく、どうして有髄細胞と無髄細胞があり、その違い(髄鞘の有無)とその作用(神経伝達速度を大きくする必要のある生物や部位では、跳躍伝導を行うから)を整理していくと統一した内容となります。 このように、整理がよければ長く記憶して忘れることがないですし、数十字から数百字で内容を説明し考察する記述式に、とても対応しやすくなります。つまり暗記にプラスした思考力が養成されます。整理された文章はとてもわかりやすく、採点や添削で高い評価がえられます。どうか、書いた文章を家庭教師や添削者にできるだけ採点してもらって、整理された具合を確かめてみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(18) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -理数系が得意な人へ もう1ランクアップするために2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前回の話で、受験生には1)理数系が強いタイプと、2)理数系は苦手だけど語学や暗記が強い人の、概ね2タイプの人がいることを説明しました。今回は、理数系タイプの人が、暗記の多い科目の勉強をする場合のコツをお話ししたいと思います。
数学や物理などの計算問題が得意な理数系の人は、暗記をとても嫌がることが多いです。話をきいてみると、丸暗記では数に限界があるからうんざりしてしまうようです。数学や物理でも基礎となる公式や考え方は暗記する必要がありますが、数が比較的少ないこと、証明などで理由付けがされているので覚える必要性がわかること、そして問題演習で何回も使用していくことから、記憶に定着していくようです。それとは対照的に、英単語や社会の年代や史実などの暗記は、なぜその単語や名前じゃないと駄目のか(例えば、なぜgoはwentや goneという不規則活用をするのか、どうしてbe interested inでは前置詞inを使用するのか、など)、特に理由もなく覚えるしかない場合も多いです。それで、覚えるのがめんどうになり正答できないことが重なると、だんだんと敬遠してますます苦手になっていく-という悪循環の泥濘にはまってしまうようです。 まずは、嫌がらずに最重要項目のみを整理してみてください。要点だけをまとめた受験参考書が役に立つでしょう。繰り返し繰り返し思い出して、それでも難しい場合には沢山書いてみたり練習問題を解くなりすれば、馴染みやすくなるのではないでしょうか。予備校や塾などで(無理強いでも)授業を受けていれば、何回も聞いて慣れてくることがあるでしょう。しかし、集団授業のペースは個人に合わせてくれないのでどうしても覚えきれないときがあります。そういう場合には、一度家庭教師に頼んでみてください。個人のペースに合わせて、覚えやすいように説明できます。頭の中で整理していくきっかけになるはずです。上手な家庭教師ほど、記憶に残りやすい説明ができます。断片的でない、他の単元や内容ともつながる説明が受けられます。それは、以前お話したように、科目に精通した教師は、印刷では伝えられない行間を伝えられるからです。数回聞いただけで、勉強の効率は10倍以上アップするでしょう。 コツが分かってきたら、より細かい項目も徐々に挑戦できるようになるでしょう。どうか、少しずつ馴れるように工夫してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(17) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -理数系が得意な人へ もう1ランクアップするために- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
みなさん、夏休みも大詰めですね。夏休みの勉強計画がはかどっている人は、その調子で2学期までがんばってください。予定より遅れ気味の人は、どうか残りの日程で少しでも成果が挙がるように奮起してくださいね。
さて、家庭教師をしていると、1)理数系が強いタイプと、2)理数系は苦手だけど語学や暗記が強い人の、概ね2タイプの人に教えることになります。 理数系タイプの人は、第1に数式を使った計算問題が得意です。多くの語句を暗記していくより、計算で勝負したいタイプです。従って、英語や国語、社会、生物より数学や物理が好きな場合が多いようです。しかしながら、計算が得意であっても、数理に大変秀でているか、数学的物理的センスに長けているか、ということと必ずしも一致していないのです。それは、論理的思考や応用的思考がどれだけ身についているか、にかかっているからです。これがないと、初歩の計算はスイスイできても、難解な応用問題、入試問題をこなすことはできません。また、大学入学後に数理系科目(解析学、幾何学、論理学、物理学など)を履修していくときに苦労するでしょう。 数学的物理的センスは、運動能力のように生まれつきの得手不得手の面もありそうですが、訓練でかなり伸びることがあります。まずは、基本問題をひととおり終えて、できるだけ多くの問題のパターンに当たってみてください。どの考え方、方法を使っていくかを数多くみていくと、大半の入試問題に使用できます。更に、発展問題に時間をかけて取り組んでいくと、数学的思考がどんどん訓練されると思います。このようなレベルの高い問題演習は、解答できない場合がしばしばあります。いつも解答できなくても、また少数の問題しか取り組んでいなくとも、どうか気にしないで少しずつ挑戦してください。解答例をよく読み、家庭教師と解答について話し合うだけでも、とてもいい練習になるでしょう。このような思考訓練を少しでもしているか、全くしていないかで、大きく差がつくはずです。 東大や京大の理系受験でも、2次試験の数学6問で満点をとるのは通常無理で(時間がかかる難問があるので)、ほとんどの受験生は、常に6,7割程度が正答できるように訓練しています。医学部受験では8割程度正答する必要がありますが、記述式試験問題の大半は頻出問題や標準問題です。やはり、日頃の訓練が第一といえるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(16) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -写真と図表のインパクト- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家庭教師として教える時一番苦心することの一つに、動物や植物、化学物質について説明をすることがあります。それは、通常生徒の目の前で実験を行ったり、生物の実物を見せられないからです。従って、写真や図表を使って説明して、できるだけ想像してもらいやすいようにするしかありません。その時、実物には及ばないものの、写真や図表がいかに助けとなるかが痛感されます。
人間が物事を認識する場合、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚などの感覚を活動させますが、知覚の半分以上は視覚でするといわれています。まさに、百聞は一見に如かず、ということです。大学や学会、会社、講演などの発表でも、ぱっと見てわかりやすい図表や字が最も重要視されます。どんなに巧みな言葉で想像を駆り立てても、初めて聞く内容、詳細な状況を把握してもらうには、限界があるといえます。それで、写真や図表をスライドで見てもらったり、カラーや字体を変えて視覚効果を上げるようにします。 生物の場合、頻出の動物や植物について、詳細な形態、特徴を覚えなければなりません。化学も、覚える物質の特徴(色、反応性、化学変化など)は多数です。勉強で、視覚効果を利用しない手はありません。語句以外の感覚を駆使して覚えることで、理解する効率は相当挙がるものです。例を挙げると、硫黄の同素体を覚えるときに、3種類の名前(斜方硫黄、単斜硫黄、ゴム状硫黄)だけではピンとこないものです。その各結晶を写真で見比べながら、各同素体の融点、分子式、特徴を覚えることによって、まとめて記憶されます。 それで、図表や写真が多い本や資料集、図表、参考書を活用することを、お勧めしています。特に、生物や化学、地学の資料集や図説がとても有効です。 例えば、 「視覚でとらえるフォトサイエンス 生物図録(化学図録、地学図録)」(数研出版)、ダイナミックワイド 図説生物(図説化学)(東京書籍)、ビジュアルワイド 図説化学(図説生物)(東京書籍)などがあります。高校や進学予備校で指定されて購入された人も多いでしょう。どれも、800円程度で、大学の受験費用や入学費用を考えれば、手元に持っていて、できるだけ見るようにすることは、とてもお安いといえます。もともと、勉強の理解や効率は、お金では変えられない貴重なものです。家庭教師も、時間を有効に使って、最も効果的に勉強するためにあります。語句(数式)と図表に加えて、音声による説明で、勉強を集約的にしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(15) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -練習問題の選びかた- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験勉強の時、受験生のみなさんは必ず何かのテキストや問題集を使って、問題を解答する練習をしています。そのとき、練習問題の選び方で、実力をアップさせる効率が、全く違うということを、今回は説明したいと思います。
解答者にとって、練習問題には2種類あります。すなわち、1)正答できるものと、2)自力で正答できないものです。自明の理かもしれませんが、そのことを改めて認識しながら、本当に必要な練習問題を効率よく選んで解かないと、とても遠回りして、入試までに間に合わないこともあります。 1) 正答できるものは、偶然正答できた場合もあるでしょうが、大抵は既に身に付けた知識や実力で正しい答えが導き出せたといえます。実力で正答できた練習問題は、現段階で更に練習する必要がないものです。それは、時期を見て忘れないように復習したり、総合問題の中で確実に得点できることを確認することで十分なものだといえます。スラスラ解答できるので、つい同じような練習問題ばかり沢山解いて、勉強した気分になりがちですが、ここが問題点になります。それよりは、自力で正答できない問題について、時間をかけて解ける実力を身につける必要があります。 2)自力で正答できないものは、更に2種類に分けられます。すなわち、 2-1)実力はある程度あるために大半は正答できるが、着眼点が思いつかないものや知らなかったものがときどきある 2-2)実力を超えた問題を選んだために、ほとんど解答できないもの、の2つです。 ともに、より実力をアップさせるために、一工夫していく必要があります。 2-1)では、問題集の中のできなかった問題を、特に復習していく必要があります。そのとき、できなかった問題が、難易度が高いものばかりであれば、そのレベルの高い問題集を別に選んで演習すると、レベルアップを狙った勉強ができます。つまり、基本や標準はほぼクリアした状態です。 2-2)では、より基本的で標準的な問題集やテキストを理解してから、その問題集にもどる必要があります。高校や予備校で使っている問題集が難しい場合には、自分用の基本問題集、参考書を入手して、初歩から勉強することが大事です(基本はとても大事なことなので、簡単な問題集を使用するのは全然恥ずかしいことではなく、むしろ褒められるべきことです)。 集団授業では、教材や進行具合が一括しており、自分の現段階に適した授業でないと、授業理解も予習復習の演習でも苦労します。その結果、1)または2)の問題点を繰り返して、折角の時間を実力アップにあてていない場合も出てきます。 その点、マンツーマンの家庭教師ですと、自分に最も適した問題のみを選択して、集中的に訓練できるという利点があります。もし、順調に受験勉強がすすんでいないと思う場合には、どうか家庭教師に尋ねてみてください。現段階をチェックして、適した練習を行う実力アップの最短コースをアドバイスできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(14) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -行間を語る教師と授業- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暑い日が続きます。夏休みも前半が過ぎました。勉強ははかどっていますか?
夏休みの過ごしかたとして、まず毎日の勉強のスケジュールを組むこと、各科目にかける勉強時間の時間配分や範囲を考えること、自分の完成度(得意不得意)を考えて勉強する本のレベル(基本、基礎、標準、上級、入試問題など)を選ぶこと、家庭教師や夏期講習、模試を利用することを語ってきました。今回は、自分ひとりで勉強する独習と、教師指導による勉強を比較して、一番効果的な勉強法について考えてみます。
独習の場合、なんといっても自分のスケジュールに合わせて自由に勉強できる利点があります。24時間好きな時間に勉強して、疲れたらすぐ休むこともできます。適した参考書や問題集を使用していれば、ある程度効果があるでしょう。しかし、大学受験の入試問題、特に難関大学の受験については、それだけではどうしても足りない場合があります。それは、自分の完成度が客観的に掴みにくい、本試験の情報や雰囲気が不足しがちだということです。例えば、問題集のうち一回目で解答できなかった問題があるとします。解答解説を読んで納得すれば、一応理解し吸収できた気持ちになります。しかし、2回目以降でまた解答できない場合、類似問題が解けない場合には、その問題を自力で解答する実力がついていないことになります。なにか違う勉強法を考えないといけません。 実は、私は独習派でした。学校で指定された教科書や参考書にプラスして、受験に向けて、少しずつ志望大学用の問題集や参考書を買って、自分でほとんど理解し大半を解答していました。夏休み中は、受験科目用に多くの高校の補習授業がありました。高3の8月中に、大手予備校の夏期講習を3授業ほど採り、大学別模試(東大理系)を受けて、B判定からC判定(合格率60%ぐらいから40%ぐらい)でした。難関大学受験に向けての完成度は、夏休み直後で60%~70%ぐらいだったと思います。ある程度理解力や学力があれば、ほとんどは入試問題に取り組めますが、最後の詰め、つまり標準問題以上の難問にも常時取り組める実力を養い、常に安定した得点をする、という点で自力では不足していたようです。 一方、教師による授業ですと、解説の文章には書いていないコツや背景を語ってもらえる利点が大きいです。解答の流れ、他の科目や単元との関連性、大学以上の詳細な知識の背景などです。塾や予備校の夏期講習は授業時間と授業内容の進行が決まっていますので、効果的か効果的でないかを判断して、適度に履修する必要があります。その点、家庭教師は、自分の完成度に合わせたサポートができます。相性がよくて、生徒の完成度や目的を把握して適度なアドバイスができる教師であれば、とても効率があがります。特に、生徒の志望大学を受験し入学している教師や、入試問題や情報に詳しい教師であれば、とても適したアドバイスが得られるはずです。たとえ、授業回数が少なくても、とても効果的です。 どうか、夏休みの受験勉強に合わせて、必要な場合に家庭教師を利用してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(13) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -夏休み対策 苦手科目の克服- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
みなさん、暑いですね。お元気ですか? 今年は、記録的な猛暑なので、特に体調管理は大事になりますね。 7月が過ぎ、8月になりました。夏休みの勉強計画の進行具合を確認する時期です。予定より随分遅れているようでしたら、もう一度夏休みの受験勉強計画を再考してみる必要があります。特に、高3生にとっては、夏休みの効率のよさが、今後の勉強に大きく影響します。受験する全ての科目をまんべんなく勉強してください。各科目にかける時間や頻度は、科目の重要性(受験科目中の配点)や、得意か苦手かで分けていくといいと思います。 特に、夏休みは、苦手科目に時間を多く割ける貴重な時期ですね。苦手科目は、基本や基礎を十分に理解していないことが、苦手の原因になっていることが多いです。夏期講習などで、いきなり本格的な入試問題や詳細でハイレベルな内容をいわれると、消化しきれないことがありますね。そういう場合は、欲張らずに基本問題集や基礎問題集、要点のまとめに絞って勉強するといいと思います。どの科目も、基本、標準、上級、難関大学受験向きと、目指す完成度で分別されて問題集やテキストが作られています。自分で取り組みやすいレベルを選んでください。夏休みを通して一通り勉強してしまえば、達成感もありますし、大きな自信につながります。 例えば、理科(生物、化学)や社会(世界史、日本史、地理、現代社会、政治経済など)でしたら、太字や赤字で書かれている用語や内容が、最も基礎的で重要なものです。それは、絶対に理解し覚える必要があります(最重要項目)。それが、全範囲に渡って完成されることを第一に考えます。その後、詳細な内容を少しずつ理解し覚えていけば、得点率がアップします。標準問題集であったり、上級レベル問題集、志望校の過去問に挑戦することになります。 自分の完成度、適切な受験の本がわからない場合には、どうか家庭教師に聞いてください。家庭教師は適切なアドバイスをしています。夏休み中に、苦手科目について2,3回尋ねてもらえれば、とても効率があがります。その後、自分で予習や復習するのが、とてもやりやすくなりますよ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(12) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -夏休み中に模試をうけよう!- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆さん、待望の夏休みですね!手放しで喜べないのが、ちょっぴり受験生のつらいところですね。主に勉強、適度に気分転換を入れて、7,8月を過ごしていきましょう。
夏休みの過ごし方については、以前もアドバイスしてきました。今回は、夏休み中に行われる全国規模の模試、特に8月に行われる志望大学別の模試を目標にして、夏休みのスケジュールを組むことをお勧めしたいと思います。 全国規模の模試(マークシート式あるいは記述式)は、大手の予備校や塾で毎月のように実施されています。高校によっては、中間テストと期末テストに加えて、実力テストとして単位評価にしています。受験者は、全国規模で何十万人にもなりますが、学校によって利用している模試が違うため、4月から6月の各模試では、受験者層の多くが抜けている状態です。 ところが、7月8月の志望校別模試には、来年の受験者層の多くが受験します。まず、地方都市にある高校生、受験生が多く受験します。夏休み期間なので、大都市以外の地域の受験生は、移動して積極的に夏期講習あるいは模試を受けます。これらの受験生は、来年受験する人達の中で、かなりの割合を占めているといえます。特に、地方都市在住で難関大学を受ける上位層の受験生が、志望大学や志望分野にあった模試を多く受けます。 地方都市の上位レベルの高校生は、大都市圏ほど塾や予備校が多くないこともあり、自習によって基礎から発展レベルの大部分を把握し理解しています。現在の受験参考書や問題集は多種多様であり、全国共通で購入できる安価なものなので、受験生が持っている本にほとんど差はないでしょう。それよりも、大都市圏では、受験に関する情報や受験場の雰囲気を日頃から享受しやすいという、圧倒的な利点があります。対照的に、大都市部でない地域の受験生は、日頃はそれらを手に入れるのに限度があるため、夏休み中に積極的に入手しようとします。特に、8月20日頃には、大手の予備校で難関大学別の模試(東大模試、京大オープン、医学系模試、私立大模試、などがあります)を実施するので、上位層の受験生は、それを一つの目標としています。 更には、自宅浪人生、再受験者(大学に合格して入学した大学生でも、第一志望の大学や志望分野を目指して再度受験する人もいます)は、日頃は受験関係の学校の授業に参加できないけれど、夏休み中の模擬試験はよく利用します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(11) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -大事な夏のすごし方 その2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月に入り、ますます蒸し暑くなりました。高校生の人たちは、期末テストや通知表の結果に一喜一憂して、夏休みを迎えるところでしょう。高卒の人は、夏の模擬テスト、夏期講習などのスケジュールを組んでいることと思います。 前回もお話したように、夏休みの一ヶ月半を効率よく乗り切ることで、9月以降がとても楽になります。9月に入ると、センター試験や私立大学の出願時期が近づいて、急速に受験の雰囲気が高まります。必要な勉強を網羅していないと、秋口からますます気持ちが落ち着かなくなります。そのような事態を避けるためにも、7,8月はしっかりした(勉強中心の)生活スケジュールをたてて、それを実行することが不可欠です。 まず、試験の時間帯に合わせた朝方の生活をお勧めします。試験は朝9時か9時半開始なので、その時間から夕方までの時間に、最も体調がよく頭が冴えていることが望ましいのです。夜型の人で、2,3日徹夜勉強をして集中的に身に付けて急速に朝方に直している人もいますが、大抵は生活習慣を変えるのに1週間から2週間はかかるものです。海外旅行で時差ボケになるのと同じように、体がだるくて頭は働かない状態になりがちです。7,8月で不規則な生活が身についてしまうと、体調を崩しやすいだけでなく、勉強の効率も総じてみれば悪くなるのが普通です。朝が苦手な人は、午前中に授業や講習、テストを入れて、絶対起きないといけないスケジュールにするなど、工夫するといいかもしれません。 また、運動不足にも気をつけてください。高校生や予備校生の人は、朝から学校に通うだけでかなりの運動になっています。しかし、夏休みに入ると、その運動消費量がなくなります。冷房の効いた部屋で、座りっぱなしで(勉強して)、冷たい飲み物を飲んで、と体に悪いことのオンパレードです。初秋には、なにかしら不調になりそうです。特に受験生は、長時間机に向かって座り、授業を受けて勉強する必要があります。これが、以外と無理のある姿勢なのです。着席では、腰に大きな力がかかり、内臓が下垂しますし、姿勢をむやみに崩す人も多いです。30分毎に立ち上がったり、軽く関節を動かすだけで、骨や筋肉、内臓に対する負担が随分軽くなると思います。受験は、体力!です。 ショッピングや本屋さんで、探しものをして買い物をするだけで、結構な運動になります。毎日24時間(睡眠をのぞいても16時間)を連続して勉強することは、まず不可能ですから、いかに数時間を集中して効率をあげるかを考えるのが一番だと思います。家庭教師は、最も効率をあげるお手伝いをしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(10) | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -時間のかかる勉強を少しずつ 国語(古文)編- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お元気ですか。実力をつけるのに時間がかかる科目(英語、国語、数学)の基礎力をつける対策を考えています。今回は、国語の中の古文について見ていきます。特に、国語の苦手な理系受験の人の参考になればと思います。 国語は、文系受験者にとって比重が大きく、得意な人も多いでしょう。しかしながら、理系受験者の中には苦手にしている人が時々いるようです。理系受験では、数学、理科、英語の勉強にどうしても時間がとられてしまい、国語の時間が確保できない傾向がありますね。しかしながら、センター試験の中で国語受験を必要とする人も多いはずです。やはり国語についても、日々の訓練をしていないと、高得点は狙えません。 筆者が受験生だった時、予備校の古文の先生が言っていたことばが、とても印象に残りました。「古文は、英語を読むのと同じだ。各単語と構文を分解して、論理的に解釈して読んでいくことだ。だから、理系の人のほうが、むしろ理解しやすいと思うよ。」確かにその通りだと思います。古文では、現代語に通じる語句が含まれているとはいえ、日頃使っていない言語を読むわけです。よほど熟達してないと、流れるように読むのはとても難しいでしょう。一語一語噛み締めるように解釈していくことが、古文の勉強の第1歩になります。日本人ではあるが、古文では「ネイティブ・スピーカー」ではないということです。 我々が日頃使用している現代日本語は、幼児の頃から長い年月をかけて身につけたものです。繰り返し繰り返し使用してきた結果、ほとんど自動的に(つまり無理に意識していなくても)、聞きとり、話し、読み、書けるようになったのです。英語についても同様で、何年かかけて難解な長文を読み書きし、話し聞くことができるようになったというわけです。(ただし、英語については、習い始めた時期や生活場所など、人によって教育背景が異なるため、熟達度に差があるでしょう。)現代日本語と英語の量に比べると、今まで読んできた(問題で解いてきた)古文の文章はとても少ないといえます。 そこで、できるだけ頻繁に古文を読み、総合問題を解答することが、古文対策で必要になってきます。 まずは、古文の重要な単語と語句・用法を確実に覚えていきます。教科書と教科書併用の注釈書、受験用参考書、要点集など多種ありますので、適した本を選んで覚えるようにしましょう。多読のためには、古文の単行本、文庫本がお勧めです。小さいサイズで安価ですし、原文と注釈が並んで書かれているのでとても便利です。筆者は、源氏物語、平家物語などを買って読んでいました。 更に、古文辞典を活用することも意外と効果的です。現代語訳、文学史、文化的背景(行事、暦)などを調べていくと、詳細なことを調べ覚えることができます。我々がお世話になる受験参考書も、元は古文辞典を抜粋して整理したものですね。時間がかかる練習なので、今のうちに試してみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(9)-大事な夏のすごし方- | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆さんお元気ですか?高校生の人は、期末テストの準備で忙しい時期ですね。卒業した人たちは、夏休みに向けて気持ちを切り替えているところでしょう。 大手予備校や塾の中には、夏期講習の募集で、夏を制する者は受験を制する!といったキャッチフレーズを使用する場合がありますが、確かにそうだと思います。特に、現役生は、大学受験に初めて向かうわけで、浪人生に比べてとても時間が限られています。浪人生が大学受験の全範囲を履修した上で、実力アップの訓練をしているのに比べると、現役生の多くは、2学期3学期で高校課程を新しく習うのです。早め早めに終わらせたほうが有利なので、中高一貫校の進学校の中には、高校の前半までに高校の全課程を終わらせてその後は受験対策ができるようなカリキュラムを組んでいるところもあるようですが、そうでない学校も多いわけで、自主的に計画をたてて早め早めの準備をすることが不不可欠です。もっとも勉強の効率がいい方法を自分で考えて、7月8月のスケジュールを組みましょう。 自習は、自律心があって、予定通り勉強をすすめられる人にはいいでしょう。各科目について、毎日何ページ進めるか、どの問題集でどのレベルの問題(基本問題、標準問題、発展問題(本格的な入試問題))をこなせるようにするか自分で考える必要があります。 自習では効率が悪い人は、学校の夏休みの補習授業をしっかり受ける方法や、予備校や塾の夏期講習を利用する方法があります。高校の補習授業は、日数や時間が限られていますが、民間の夏期講習は、各科目に様々なコースがあり、自分に合わせて選択できます。集中したい科目や単元を数日間だけ受講して、あとは自分で宿題や自習をしっかり行う方法もあります。また、自分ひとりではどうしてもうまく進められないという人は、いくつかの夏期講習を選択すれば、授業にでて勉強せざるをえないのでいいかもしれません。授業ですと、講師が流れを作ってくれるメリットがあります。 しかし、なんといっても最も効率がいいのは、1対1で自分に合った流れをつくってくれるマンツーマンの授業ですので、うまく家庭教師を利用してください。志望校の様子や、受験への準備などいろいろアドバイスしてくれますよ!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 2004年度入試結果分析報告 | 教務部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.人口動態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年度は再び18歳人口の減少幅が拡大しました。01年から03年にかけての3年間は減少幅が少なかったのですが、04年は5万1千人減と大幅に減少しました。また05年も引き続き減少幅は大きく6万5千人減となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料1】18歳人口の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:1000人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.国公立大の動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【資料2】 国立大センター試験・教科・科目パターン別募集人員占有率の変化(2003vs2004)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料3】 センター試験志願者数の推移 (現行教育課程移行後)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※文部科学省資料より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料4】 国公立大学 入試日程別志願状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※文部科学省資料より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料5】 主要国立大学 志願者数の2003年度vs2004年度比較
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料6】 国立大医学部の難易度
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.私立大の動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料7】法学部の定員削減(減少大学のみ掲載)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料8】04年度入試難易度予想比較(私立大医療系)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【資料9】2005年度新設予定大学一覧(2004年5月発表)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(8) | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 時間のかかる勉強を少しずつ 数学編 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間をかけてコツコツと練習しなければできないことがあります。それは、例えて言えば、スポーツや音楽の基礎トレーニングのようなものです。どんな天才でも、全く基礎練習をしないで永続的に高いレベルを維持することは不可能であり、なんらかの形で訓練や修行をしています。 数学は、好き嫌い、得意不得意の差が激しい科目です。数学での受験を敬遠して、学部学科を選択する受験生も少なくないでしょう。数学は、1つ理解できない理論や公式があると、それが行き止まりとなって次の理解ができなくなることや、1問の配点が大きいことがあり、実力差が出やすい特徴があります。 数学が得意な人は、論理立てて考察することと難問を解答する楽しさを知っている人です。好きだ、得意だと感じるので、時間をかけて問題を解くことが苦痛ではないわけです。理科の物理には、微積分や三角関数を使用して理解し計算する要素があるので、数学の応用の1つといえるでしょう。「大学への数学」(東京出版)のシリーズは、数学をマスターしていくうえでとても手ごたえがあります。解答の着眼点が面白いので、物理学科や数学科に進む人も好んで問題集に用いているようです。 一方、数学を不得意と感じる人は、1つ理解できないことで悪循環に陥っているといえます。嫌いだから演習しない、だからますます理解できないことが増えるといった具合です。この悪循環をどこかで切らなければ、数学で少なくとも単位を修得し、更には受験することは難しくなります。 対策として、1)基本問題に絞って繰り返し演習すること、2)理解しにくい問題は暗記してしまい、類似問題を幾つか解いてみること、をまず提案します。1)に関して、基本問題のみをうまくまとめた問題集もあるし、教科書併用の問題集も、通常は基本問題、標準問題、発展問題とレベル分けがされているので、基本問題のみに絞ればいいわけです。教科書は、重要な公式や定理がどうしてできたのか、なぜ暗記しなければならないのかが、証明を用いて書いてあります。本当はその証明の成り立ちから理解していかなければならないのですが、どうしても難しい、間に合わないという場合にはなんとか基本だけでも覚えることを考えます。2)のように、最初は解答例を丸ごと覚えて、よく似た問題を何度か解きます。しばらく時間をおいて、同じ問題を解いてみれば、覚えたかどうかを確認できます。 高校時代、予備校時代、大学学部時代を通じで、筆者の多くの同級生を見ていると、ある傾向に気がつきました。女性はコツコツとまじめに勉強しているタイプが多いのに比べ、男性は短期集中型(悪く言えば直前に徹夜をしてまとめて勉強している)人が結構目立つのです。短期集中型でうまくいく場合には、教科書や宿題を通じで基礎を完全に理解していて、すぐに応用に持っていけた場合だと思います。通常は、少しずつ練習して積み上げていかないと、隙のない難解なレベルまで実力をつけるのはとても難しいです。女性は数学に苦手意識をもつ場合が多いといわれていましたが、コツコツ型にうまくのせれば結構向いていると思うのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(7) |
東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 時間のかかる勉強を少しずつ 英語編 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お元気ですか。来年の受験までにまだ半年以上あるので、たっぷり時間があると感じられるかもしれません。だからこそ、今のうちに実力アップに時間のかかる勉強をしておく必要があります。 英語、国語、数学は実力をつけるのに時間がかかる科目といわれています。毎日少しずつ演習し、単語熟語を覚えていかないと、短期間ではとても消化しきれないことがあるからです。実力を少しでもアップするのに3ヶ月はかかるともいわれます。一方、社会と理科は内容量が多いですが、英国数よりは短期間で完成しやすいといわれることがあります。英数国で基礎力が鍛えられていれば、直ぐに理科と社会に応用できるからでしょう。 大学受験の英語では、少なくとも5000語以上の単語、数百個の重要な英熟語、数十個以上の重要構文、英文法の重要事項などを覚える必要があります。覚えやすいものは一度で暗記できるかもしれませんが、数回は読み書きして使用しないと確実に整理して暗記しにくいことがあるでしょう。数が膨大ですので、例えば1日のノルマを決めて覚えると習慣になって覚えやすいと思います。1日に20語覚えれば、1週間で140個、1ヶ月で600個、半年で約3600語になります。 センター試験の英語は比較的容易な文章ですが、国公立大学2次試験では高度な文章を出題するところもあり、知らない単語が含まれている場合がよくあります。しかし、あまり気を取られることはありません。単語を整理して覚えておけば、単語の一部分(例えば、接頭のpre(「前」の意味がある)、ex(「出る」、「外」の意味がある)など)の意味を捕らえて、ある程度は単語の意味を予想することができます。多読して、長文を読む力が鍛えられていれば、文章全体の流れからでも、かなり不明な単語が予想されます。 日本の大学受験の英語は高レベルですので、日本人が英語を読み書きする力はかなり高いです。資格や海外留学、海外派遣のために国際認定された英語の試験を受ける場合でも、大学受験までの内容で概ね対応できます。例えば英検や、TOEFL (アメリカの民間会社が英語を母国語としない人たちのために提供している英語の試験で、聞き取り、英文法、英作文、長文読解に分かれている)、TOEIC(こちらもTOEFLと同じ会社が提供している試験ですが、英会話の読み書き聞き取りが中心で、TOEFLより内容はやや易しいといわれている)を受験しても、大学受験をこなしていればとても楽です。苦労するとしたら、、日本人は概して英語を話したり聞いたりする練習ができる機会が少ないので、これらの試験の聞き取りは難しくて大変なことがあることや、高得点を狙うためには出題形式の特徴に慣れることです。しかしながら、大学受験のヒアリングテストは、スピードがゆっくりで2回繰り返して音声を流す場合がほとんどなので、英語の基礎力ができていれば大丈夫です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(6) - 理系科目の選択 - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月に入って紫陽花の季節になりました。雨天の時、勉強の合間にしっとりとした紫陽花の青色を見ていると目が休まりますね。 紫陽花は、和名でアジサイ、学名でHydrangea macrophylla D.C. var. hortensia REDH.、英名でHydrangea(学名と同じで、水瓶の意味が由来)で、日本は原産地の一つです。日本国内に自生していた地味なガクアジサイを、人間が見栄えがよくなるように育種改良し、ガク片が目立って中心部の花(真の花)が目立たない現在のような花ができました。18世紀後半に、カール ピーター ツンベリーによってヨーロッパに紹介され、ドイツ医師シーボルトやロシア人植物学者マクシモウイツによって日本のアジサイがヨーロッパに渡り、交雑によって西洋アジサイが生まれました。いまでは、ヨーロッパでも最も使用されている花の一つとなっています。土壌成分の違い(青色のガク片になるには、土壌の硫酸アルミニウムが関係していることが研究報告されています)、酸性度の違い(酸性に傾くと青色、アルカリ性だとピンク色になる傾向があります。リトマス紙と逆ですね)落葉性低木で、挿し木繁殖されます。これは、遺伝子型が全く同じクローンを増やして、よい性質を保存した植物を栽培して、市場に出荷するためです。ちなみに、日本全国にある(おそらく数千万本?)ソメイヨシノは、江戸時代に育種されたクローンが挿し木繁殖であちこちに散らばったものです。遺伝子型は同じですが、環境(例えば年平均気温の違う北海道と東京)によって、開花時期が異なったりします。 以上のように、アジサイを取り上げただけでも、多くの科目(生物、化学、英語、世界史、日本史、地理など)が関係しています。英語は、どの学部学科の入学試験でも出題されるので、必ず勉強することになりますが、理科や社会は選択科目がいくつかあるので、受験を考えると選択時にいろいろ思案することがあるでしょう。受験を突破するためには、自分の得意(得点がより高い)で興味のある科目を選択することが必要ですが、選択しなかった科目でも入学後に必須となる場合が結構あります。例えば、医歯薬系を目指す場合、物理化学で選択しても、医学に最も近い生物学(遺伝学、分子生物学など)は入学後多く勉強することになりますし、逆に生物化学で選択しても、物理的特性を学んで医療機器を使用する必要性から、物理は教養科目で必ず習います。これは、生物化学系に進学する人に共通して言えることで、入学後は履修しなかった科目も独学で勉強することになります。社会の科目選択でも、どの科目が負担が大きいか、センター試験で楽かなどどいろんな情報が入ってくるでしょう。まずは受験突破のため、そして受験後の専攻のために、科目をじっくり選んでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(5) - 医歯薬学部への向けて - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回は、理系科目を得意にするための読書を考えました。今回は、医学(医学科、保健衛生学科、理学療法科、作業療法科、栄養健康学科、放射線技術科学科など)、歯学、薬学部を目指す人のための生活信条を考えたいと思います。 これらの学部学科を受験する人は、英語に加え、数学、理科、小論文(東大は国語)、面接が科されることがほとんどです。国公立大学では、前期試験と後期試験で試験内容にかなり違いがありますが、根底は同じです。すなわち、受け入れる大学側は、医療に関わるものとして、その分野の背景をどれだけ理解しどのような決意を持っているか、どんな人間性かをみたいということです。これらの学部学科を修了すれば、国が認定する資格の受験資格、すなわち、医師、歯科医師、看護師(以前は女性を看護婦、男性を看護士などと呼び分けていましたが、現在は性別に関係なく専門職として統一した名称になりました)、保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法師、作業療法士、薬剤師といった受験資格が得られ、その試験に合格すれば医療に携わり他人の健康や生死を左右する立場になるわけで、大学側としても責任重大です。特に、最近は医療ミスが増発しマスコミも大いに注目するようになりました。医療ドラマや小説、漫画も多いし人気がありますね。 人間性あるいは人格というものは、日々の生活の中で自覚してつくっていくものです。20歳ぐらいまでは親や周囲の大人達の習慣、マスコミや音楽などに影響を受けることも多いでしょうが、大学受験でどのような人間性に見られるのかは自分自身の責任となります。自己が元来単独で持っていた気質や習慣と、他者から影響を受けた部分が統合されて、自分自身の性格や思考、習慣を形成しています。特に、思春期を過ぎ自我意識や思考が発達してくると、自分独自のものを強調したいという願望が強くなりますね。他者から受ける影響がいい影響であろうと悪い影響であろうと、最終的にはそれを取り入れると決定したのは自分自身であるということを自覚して欲しいと思います。中にはとても気の毒な環境で深刻な影響を受けてしまうことがあるかもしれませんが、見聞きし話しあうことができる人間は沢山います。その人たちは、様々な考え方ややり方を持っています。誰もがいい面も悪い面も必ず持っています。どうかいい面を鋭敏に知覚してうまく自分の中に取り入れて欲しいと思います。悪い面は、その人を憎んだり卑下するためのものというより、自分がそうならないための戒めであり、気の毒なことなのです。自己に優しく他者に厳しくすることは容易ですが、その逆は難しいものです。しかし、医療に携わる専門職では、そのような広い潜在能力をまず必要とされるのではないでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(4) - 読書で基礎力をつけよう - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その2;理系科目のための読書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験生の皆さん、調子はいかがですか?前回は、読書の効用について考えました。今回は、その続きです。 理系科目というと、数学や物理の計算がまず思い浮かぶ人も多いでしょう。それだけで、どうしよう!と逃げ腰になるかもしれませんね。確かに、日々問題演習することがとても重要になってきます。しかし、重要公式は最終的に暗記するようになりますし、研究発見のめざましい分野(遺伝子学や分子生物学、生化学など)の分野では、最新の研究成果が受験問題になったり、大学入学後に必須科目、専攻分野になることも多いので、日頃からセンスを磨いておくこと、重要な用語を覚えていくことが必要になります。特に、医歯薬学系の受験には欠かせないことでしょう。入学後の教養科目(1、2年で履修する科目)の数学、物理、化学、生物系の内容を考えても、主に大学受験までの内容が基礎になっていて、大学ではそれにプラスαの細かい専門的内容が少し入ってきます。ですから、大学受験までにしっかり基礎固めをしておくことで、大学生になってからとても講義についていきやすくなりますし、差がつくと思います。 高等学校用の参考書も、カラフルに整理されて分かりやすいものが増えました。特に、理科(物理、化学、生物、地学)と社会(世界史、日本史、地理、政治・経済、現代社会、倫理社会)で目につきます。例えば、数研出版や文英堂のシグマシリーズなどがあります。これらだけでもかなり細かい内容が書いてありますが、科学的センスに鋭くなるためには、もう少し科学的情報や記事に触れたほうが絶対にいいです。 ブルーバックスシリーズ(講談社)は、多様な分野について多くの本が出ています。内容も、とても易しく解説したものから、かなり専門的なものまでありますので、自分に適したものが必ずあるはずです。サイズも小さくて、電車の中で立ちながら読めますね。同様に、岩波新書や講談社文庫などの自然科学系の本もお勧めです。もう少し、詳細で本格的な内容に触れたい人は、UPバイオロジーシリーズ(東京大学出版)や、英文科学雑誌の和訳(サイエンス、ネイチャー、サイエンティフィックアメリカンなど)に挑戦してみてはいかがでしょうか?和訳でなく英訳版に挑戦することで、科学英語の訓練にもなります。ちょっと難しいかな? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(3) - 読書で基礎力をつけよう - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験生の皆さん、お元気ですか?連休も終わり、中間テストの期間ですね。また、浪人の人であれば、再度受験を発起して1ヶ月経った頃、1回目の模擬試験をする頃でしょうか。 とにかく、受験までまだあるということで、切羽詰まってはいない時期ですね。ある意味、揺るぎない基礎力をつける時期でもあります。そこで、できるだけ読書することをお勧めしたいと思います。 教科書や参考書は受験や試験に直接関係したものですが、そこから離れてたジャンルの本や文章でも十分に受験に役立つものが多いのです。よくいわれるのが、新聞の社説を定期的に読むことですね。現代国語の問題に出題されたり、社会(政治経済、現代社会、歴史など)に最近の動向として取り上げられることもあるので、特に文系の人には社説を読むことが必須になってきます。また、小論文が2次試験の科目となっている大学、学部を受験する人は、社説が論題として採りあげられやすいことから考えると、大手新聞社の社説に目を通しておくことが必要になってきます。 自分の興味がある分野、受験する分野がある程度分かっている人は、その分野に関連した多くの本、雑誌、記事に日頃からできるだけ親しんでおくことで、確実に実力がアップできます。 例えば、国文学関係であれば、新聞だけでなく、小説、雑誌(週刊誌、月刊誌など)、文庫本などあらゆるジャンルの本を多読することで、読むスピードがアップします。また、感性の光る文体や筋の通った文章と、そうでない文章両方に触れることによって、文章を識別するセンスを養うことができます。それは、自分が作文を作成する時にとても参考になるのです。一流の作家の洗練された文体までいかなくても、気の効いた言葉を真似して引用することで、作文が引き締まります。漫画でも、史実や小説などを背景にした緻密なものもあるので、読んでいると史実の暗記に以外と役立ったりします。 好きこそものの上手なれ、です。好きであれば、自ら進んで沢山の練習、読書を積むものです。それは、好きでない者にとっては苦痛以外のなにものでもない、できるだけ減らしたいものなので、不思議でもあり羨ましくもあります。誰しも、好きな得意な分野と好きでない苦手な分野が必ずあります。どうか、好きで得意な分野でまず実力をつけて自信をもってください。その自信が、苦手分野を克服する原動力ともなります。 次回は、科目毎にお勧めの本を紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(2) - 次の一歩 - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験生の皆さん、お元気ですか? この連載は、今回で第2回目ですね。第1回目の前回は、はじめの1歩ということで、自分に合った参考書や問題集をまず自分で探してみることを提案しました。沢山の本を見比べてみて、自分にぴったり合った本を見つけだすのは、時として難しいこともあるでしょう。そんな時は、受験の先達からアドバイスをもらうことで、解決の糸口が見つかる場合があります。 受験の先達って誰?と思われましたか? そうです、既に受験を経験した、学校の先生、塾の先生、家庭教師、両親や兄弟、先輩、従兄弟、近所の知り合いなどなどいろんな人が考えられます。聞きやすい人から、わかりやすい参考書があったら教えて欲しいと、聞いてみればいいのです。きっと、自分は受験の時にあの参考書のシリーズを頼りにしていた、などど教えてくれるでしょう。あの頃はこういう内容を習っていてこういう試験だったけど、最近は内容が変わったな、などど話が盛り上がるかもしれませんね。例えば、最近では、英語の試験でヒアリングが含まれることがどんどん増えてきましたが、以前は全くありませんでした。中学校に入学して英語を習い始める時、NHKのテレビやラジオの英会話番組を見聞きすることを薦められることは、今も昔もよくあることですが、試験が必修になってくるとなると、昔の生徒ほど気楽に聞きにくいかもしれないですね。 そして、思いだして欲しいのは、受験のアドバイスについては、家庭教師や塾、予備校の講師は専門で行っているということです。そのことは学校の先生達も行っていますが、職務の一部としてです。対照的に、塾や予備校はその仕事が全てです。個人では、自習や受験情報の収集に限界があることがとても多いので必要になるわけです。集団授業は、複数の生徒が同じ内容を習っているので、どれだけ理解し修得したかは個人差がつくものです。独学でほとんどマスターしてしまう要領のいい人は少ないと思います。それを補うのは、家庭教師(個別講師、チューター)となるわけです。適切な家庭教師であれば、生徒の理解度や到達度を把握し、効果的な勉強法や本を教えてくれるはずです。どうか、気軽に尋ねてみてください! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 難関大への受験(1) - はじめの一歩 - | 東京大学農学博士 安達 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験生の皆さん、新しい季節がやってきました! 気分を引き締めてがんばっていきましょう。まずは、はじめの一歩から、です。このコーナーでは、皆さんが受験する際に、ちょっと役に立つ話を毎回していきます。今回は、第1回ということで、新たに準備することを考えてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 自分に合った参考書、問題集を探してみよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新学年になった人は、新しい教科書、問題集をもらう時期ですね。塾や予備校に行く人は、そちらでもまたテキストなどどっさりもらうことになります。今後の予習復習のことを考えると、お腹はいっぱいにならないけど、頭がいっぱいになるかもしれませんね。 宿題をする教科書や問題集は必ず使っていきますが、実は本というのは人との相性に似ているところがあるのです。幸運にも、自分に相性のいい本に当たれば、とても理解がすすみます。文章も読みやすくなじみやすく、図表や写真は見やすいし整理して覚えやすいものです。反対に、不幸にも自分と相性がよくないものに当たった場合は、同じ内容が書かれていても、読みにくいしわかりにくいし、図表を見ても、整理して覚えることができにくいのです。理解できるものでも理解できなくなって、この科目や単元は難しい!嫌い!苦手!なんて決めつけて敬遠することになってしまったら、とてももったいないことです。 今から何回か授業を受けて、なんとなくなじみにくい、スムーズに使いにくいと思ったら、一度本屋さんや図書館で、同じ内容の本、特に参考書や問題集、教科書などを探してみることをお勧めします。同じ内容でも、沢山の出版社が様々な編集様式で出版しています。例えば、同じ算数や数学の参考書でも、分厚いもの、問題集と細かい解説が一緒にあったものもあれば、暗記のための公式だけを集めたミニ本や、10日間完成なんて呼んでいるとても薄い問題集もあります。ある本はカラーで沢山イラストや写真を掲載してるかとおもうと、別の本はモノクロで地味な感じがします。理解できなかった内容を読み比べてください。もし、ああ、この書き方なら少しわかってきた!という本があったら、相性がいい本に出会ったことになるかもしれません。買う余裕がある限り、できるだけ買ったほうがいいでしょう。参考書や問題集は元来割と安い値段です。とても大切な内容なら、それが理解できるかどうかで、勉強についていけるかどうかの重要なカギを握っているともいえるのです。不得意科目になるか、得意科目になるかは、ちょっとした説明の仕方の違いで大きく変わることがあります。どうか、仲のいい友達を見つけるように、馴染みやすい参考書や問題集を見つけてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||